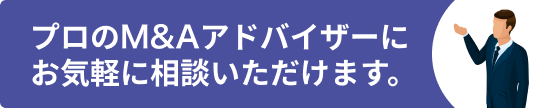エンジェル税制とは?投資時と売却時の優遇制度も徹底解説
公開日:2022年1月20日 最終更新日:2022年11月18日

エンジェル税制は、ベンチャー企業への投資を促進するために設けられた措置で、個人投資家とベンチャー企業の双方にとってメリットのある制度です。しかし、エンジェル税制の適用を受けるためには、一定の要件と所定の手続きが必要になります。本記事ではその概要を解説します。
目次
エンジェル税制とは
エンジェル税制とは、エンジェル投資家のベンチャー企業に対する投資を促進するために設けられた税制上の優遇措置のことをいいます。
エンジェル投資家とは、ベンチャー企業に出資する個人投資家のことです。一定の要件を満たす非上場企業のベンチャー企業に投資することで、投資時点と、投資後に株式を売却した時点の双方で優遇措置を受けることができます。
エンジェル投資とベンチャー企業の双方にとってメリットになる制度ですが、制度の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があり、また、投資の方法によって手続きが異なったりするため、制度を利用するにあたっては注意が必要です。
投資時点での優遇措置
投資時点で受けられる優遇措置には、優遇措置Aと優遇措置Bの2つがあり、それぞれから選択することができます。
優遇措置Aとは、ベンチャー企業への投資額から2,000円を控除した額をその年の総所得金額から控除できる措置になります。ただし、控除できる投資額には上限があり、総所得金額×40%か1,000万円のいずれか低いほうになります。なお、優遇措置の対象は、平成20年4月1日以降の投資が対象です。
一方で、優遇措置Bとは、ベンチャー企業への投資金額をその年の他の株式譲渡益から控除できる措置になります。控除できる投資額に上限はありません。
エンジェル投資家が未上場のベンチャー企業の株式を売却して損失が発生したときは、他の株式の売却によって得た株式譲渡益とその損失を相殺することができます。
また、その年に相殺しきれなかった損失については、翌年以降3年間にかけて株式譲渡益から損失を相殺することができます。さらに、ベンチャー企業が上場せずに破産や解散等をした場合も同様です。
ただし、ベンチャー企業に投資した年に上記優遇措置AとBののいずれかの措置を受けた場合は、取得価格から優遇措置の控除対象金額を差し引いて売却損失を計算します。
優遇措置を受けるための要件
エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、ベンチャー企業側の要件と個人投資家側の要件を満たす必要があります。しかし、ベンチャー企業側の要件と個人投資家側の要件はそれぞれ異なりますので、ポイントをおさえることが大事です。
対象となるベンチャー企業の要件
優遇措置の対象となるベンチャー企業の要件は、優遇措置AとBでそれぞれ別途異なる要件が定められています。ここでは、その概要について解説します。
優遇措置Aの要件
優遇措置Aが適用されるための要件は、以下の4つのパターンの設立年数によって異なります。
①設立後1年未満かつ最初の事業年度が未経過の場合
研究者や新事業活動従事者の人数が2人以上かつ常勤の役員・従業員の10%であること
②設立後1年未満で最初の事業年度を経過した場合
上記要件に加えて直前期までの営業キャッシュフローが赤字であること
③設立後1年以上で2年未満の場合
上記②の要件に該当するか、または、試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用含む)が収入金額の3%超で直前期までの営業キャッシュフローが赤字であること
④設立後2年以上で3年未満の場合
試験研究費等が収入金額の3%超で直前期までの営業キャッシュフローが赤字であること、または、売上高成長率が25%超で営業キャッシュフローが赤字であること
優遇措置Bの要件
優遇措置Bを受けるための要件も、以下4つのパターンのように、設立からの経過年数によって異なります。
①1年未満の場合
新事業活動従事者(研究者含む)が2人以上で、常勤の役員と従業員の10%であること
②1年以上かつ2年未満の場合
上記①の要件に該当するか、または、試験研究費等が収入金額の3%超であること
③2年以上かつ5年未満の場合
試験研究費等が収入金額の3%超、または、売上高成長率が25%超であること
④5年以上かつ10年未満の場合
試験研究費等が収入金額の5%超であること
対象となる投資家の要件
対象となる個人投資家の要件は、
①金銭の払込により、対象企業の株式を取得していること
②対象企業が同族会社である場合、保有割合が大きい上位3位までの株主グループの保有割合を加算し、その割合が初めて50%超になる時における株主グループに個人投資家が属していないこと
になります。
なお、これらの要件は、投資した年の減税措置の場合と、売却した年の減税措置の場合ともに共通の要件になります。
エンジェル投資の方法
個人投資家がエンジェル投資をする方法には、直接投資による方法、認定投資事業有限責任組合を経由する方法、認定クラウドファンディングを経由する方法があります。
ここでは、それぞれの投資方法についての概要を解説します。
直接投資
エンジェル投資家がベンチャー企業に直接出資をする方法です。主な流れとしては、ベンチャー企業へ投資することが決まったら、ベンチャー企業と投資契約を締結します。
その後、ベンチャー企業にて、エンジェル税制適用のための確認を本店所在地のある都道府県に申請し、確認書類をベンチャー企業から受け取る流れになります。
認定投資事業有限責任組合を経由して投資
直接投資の他、認定投資事業有限責任組合を経由して投資する方法があります。認定された投資事業有限責任組合に資金をプールし、ベンチャー企業に投資する方法です。
投資事業有限責任組合とは、投資有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合を指します。
具体的な流れとしては、まず投資事業有限責任組合契約を締結し、認定申請書等を中小企業庁創業・新事業促進課エンジェル税制担当者に提出します。その後、経済産業大臣の認定書の交付を受けたら、ベンチャー企業に投資するという流れです。
参照:認定投資事業有限責任組合経由-エンジェル税制申請から確定申告までの流れ-|中小企業庁
認定クラウドファンディングを経由して投資
経済産業大臣から認定を受けたクラウドファンディングを経由して投資する方法です。まず、クラウドファンディングを運営する業者は、認定申請書等を中小企業庁創業・新事業促進課エンジェル税制担当者に提出し、経済産業大臣から認定を受ける必要があります。
投資家は、認定を受けたクラウドファンディングを経由してベンチャー企業に投資した場合、クラウドファンディング業者から所定の確認書の交付を受けて、確定申告という流れになります。
参照:認定少額電子募集取扱業者の電子募集取扱業務による取得-エンジェル税制申請から確定申告までの流れ-|中小企業庁
確定申告
投資家は所轄税務署に対して、所定の書類を確定申告時に提出することで税制優遇措置を受けることができます。
ただし、確定申告の際に提出する書類の中に、ベンチャー企業から提出してもらう書類を添付する必要な場合もあるため、早めの準備が必要です。
参照:確定申告手続き-エンジェル税制申請から確定申告までの流れ-|中小企業庁
節税額の計算例:優遇措置Aと優遇措置Bはどちらが得か?
優遇措置Aと優遇措置Bのどちらが得になるかは、個人投資家の所得額や投資額によって変わります。
以下では、具体例を用いて説明します。なお、所得税の計算は「所得税速算表」に基づいて、株式譲渡課税の税率は15%とします。
例えば、総所得金額が1,200万円、企業への投資額300万円、他の株式の譲渡益300万円の個人投資家Aさんがいたとします。
優遇措置Aを選んだ場合、総所得金額から控除される額は2,998,000円(=投資金額3,000,000円-2,000円)です。
これをもとにエンジェル税制を利用した場合の支払税額を算出すると、((12,000,000-2,998,000)×33%-1,536,000円)=1,434,660円に、株式譲渡課税450,000円(3,000,000×15%)を足した1,884,660円がその税額になります。
これに対して優遇措置Bを選んだ場合の支払い税額は、投資額と他の株式の譲渡益は相殺されるので、12,000,000円×33%-1,536,000円=2,424,000円が支払税額になります。
Aさんの場合は、優遇措置Aが有利です。
一方で、総所得金額が300万円、企業への投資額100万円、他の株式の譲渡益100万円の個人投資家Bさんがいたとします。
優遇措置Aを選んだ場合、総所得金額から控除される額は998,000円(=1,000,000-2,000円)です。
これをもとにエンジェル税制を利用した場合の支払税額を算出すると、((3,000,000円-998,000円)×10%-97,500円)=102,700円に、株式譲渡課税150,000円(1,000,000×15%)を足した252,700円がその税額になります。
これに対して優遇措置Bを選んだ場合の支払い税額は、投資額と他の株式の譲渡益は相殺されるので、3,000,000円×10%-97,500円=202,500円が支払税額になります。この場合は、優遇措置Bが有利です。
出典: コラム 優遇措置Aと優遇措置Bはどちらが有利か|東京都産業労働局
ベンチャー企業がエンジェル税制の適用を受けるための手続き
ベンチャー企業がエンジェル税制の適用を受けるためには、ベンチャー企業自身で税制適用の要件を充たす企業であることや投資したこと等の確認申請を都道府県にする必要があります。申請を受けた都道府県は、確認後、確認書をベンチャー企業に交付します。
交付を受けた確認書をベンチャー企業は個人投資家に提出し、個人投資家は税務署に確定申告をして手続きが完了です。
まとめ
エンジェル税制は、個人投資家とベンチャー企業の双方にとってメリットが受けられる措置です。しかし、優遇措置を受けるためには一定の要件を満たし、所定の手続きを経る必要があるため注意が必要です。
なお、資金調達に興味をお持ちの企業はM&Aクラウドへご相談下さい。