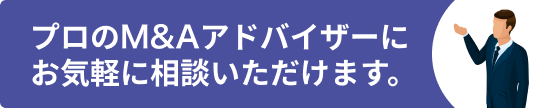株式会社の売買とは?知っておきたい売り手のメリット5つや売買方法と手順も
公開日:2022年1月20日 最終更新日:2023年1月17日

本記事では、後継者不足などで事業の廃業を検討されている経営者の方に、廃業の他にも会社の売却という選択肢があることを紹介しています。会社の売却をするためにはどういった手続きを踏めばいいのか、M&Aの手法はどういったものがあるのかまで説明しています。
会社売却の現状について
「会社を任せられる後任者がいない」、「うちの会社はもう廃業にするしかないかもしれない」といった後継者不足の悩みは、少子高齢化に伴い徐々に増えています。しかし、廃業してしまうと、その後の従業員に迷惑をかけてしまう可能性もあり、簡単には廃業できないのも事実です。
本記事では、こうしたお悩みをお持ちの経営者の方のために、会社の売却という選択肢のご紹介をしていきます。会社売却には廃業にはないメリットも多くあるのです。
会社売却とは
会社売却とは、その名の通り会社を第三者に売却することをいいます。会社売却には大きく分けて事業譲渡と株式譲渡の2種類があります。
この2つは、事業のみを売却するのか、それとも会社の株式を売却するのかで大きく変わります。
会社売却の検討理由は様々ですが、後継者不足や、不採算事業の切り離し、経営者のエグジットなどが理由としてあります。
こうしたM&Aは少し前まではあまり良くないイメージがありましたが、今は一般的なものとなっています。
もちろん廃業という選択をすることも可能ですが、自社の従業員のみならず、長年の取引先に迷惑をかけてしまうという経営者の不安が残っている場合は、会社売却が適しているといえます。
M&Aの売り手の5つのメリット
日本におけるM&Aは、毎年増加の傾向にあります。M&Aによってメリットがあるために増加しているのです。ここからは、M&Aにおける売り手のメリットを5つ紹介します。
1:従業員を解雇しなくてすむ
まず1つ目のメリットは、従業員を解雇しなくて済むことです。特に長年オーナー企業の社長が引退する際に頭を悩ませるのはその後の従業員の雇用を気にすることではないでしょうか。
M&Aにより新たな買い手が見つかれば、従業員を解雇することなく社長を引退することが可能です。もちろん、その後も従業員が安定して働くことができるかは会社の買収先が会社をどう経営していくかにかかってきます。
そのため、重要なことは、新しい経営者が信頼に足る人物なのかをしっかりと確認することです。デューデリジェンスや関係者からのヒアリングを実施し、経営者がどういった人物なのかを見定める必要があります。
2:後継者育成が不要になる
2つ目のメリットは、会社売却により後継者問題が解決することです。特に、少子高齢化が進んだことにより、事業承継をさせたくても、肝心の後継者がいないという問題があります。
また、後継者はいるものの、まだ経営をするのには経験が足りないことや、後継者が会社を引き継ぎたくないとのケースもあります。
M&Aをすることで、新たな経営者を迎え入れることができます。何よりも、その後継者は現経営者が見定めることができるのも大きなメリットといえます。
3:売却・譲渡益の獲得
3つ目のメリットは会社売却をすることにより、売却・譲渡益が見込まれることです。
経営者を引退した後は、会社売却で得た譲渡益を使ってリタイア後の生活を楽しみたいという方も、その後新しい事業を0から作っていきたいという経営者もいることでしょう。
どちらの選択をするにせよ、お金は必要になります。また、今までの役員報酬とは異なり、事業規模に応じたまとまった売却益・譲渡益が入る可能性が高いため、今後のライフプランを再度検討することも可能となります。
一方で、会社が債務超過をしているなど、企業価値が大きく下がってしまっている場合は売却をしても利益が出ない可能性もあるので注意が必要になります。
4:売却先の資本で安定経営
4つ目のメリットは売却先の資本で経営が安定する可能性があることです。
資本力が大きな企業に売却することで、会社経営が安定化し、従業員にとってもさらに安定した会社として経営を維持できる可能性があります。
特に、売却先によっては両社の販売経路やリソースを活用し、さらなる事業の発展への第一ステップとなる可能性も高く、互いのシナジーを活用してさらに会社が発展する可能性もあります。
5:負債や社長個人の保証債務がなくなる
5つ目のメリットは会社を売却することで、負債や社長個人の保証債務が解消される可能性もあります。経営者保障は国からの要請もあり、金融機関も経営者保証を外す動きは少しずつ広がってきています。
しかし、金融機関には前例踏襲の文化もなお根強く残っており、事業承継後も新経営者に担保や経営者保障を求めるケースも少なくありません。
会社売却であれば、経営者も一新されるため、一度保障を全て解消するのが基本になります。
このため保証債務を解消できるのはメリットといえるでしょう。
買い手はどう探せばいいのか
それではM&Aの買い手はどのように探せばいいのでしょうか。一口に会社を売り買いするといっても、M&Aの情報は秘匿性が高く、安易に公の場に出してしまえば、社内や取引先にも大きな混乱を巻き起こしてしまう危険性もあります。
こうした事態を避けるためにも、買い手企業は慎重に検討する必要性があります。
1:M&Aプラットフォームを利用
M&Aプラットフォームを利用するのが1つ目の選択肢です。買い手企業の探し方の中で簡易であり、敷居も低いのがM&Aプラットフォームです。
M&Aプラットフォームを利用すると、経営者の目で買い手にはどういった先があるのかを探すことができます。もちろん、具体的な交渉段階になるまでは、会社名などは伏せて交渉になりますが、他人任せではなく自社で検討できるのは大きなメリットといえるでしょう。
アプリなどを使用できるプラットフォームもありますので、会社売却を検討される際には敷居が低い手段だといえます。
2:M&A仲介業者
M&A仲介業者に依頼をするのも買い手企業を探す際の手段の1つになります。M&A仲介業者を利用すると、今までM&Aに携わってきた専門家たちからアドバイスを受けながら、会社売却について検討することができます。
料金がM&Aプラットフォームに比べると高くなってしまうのはデメリットですが、近頃では成功報酬型の仲介業者も増えており、契約まで至らなかった場合には費用はかからないという業者も増えています。
一方で、成功報酬の場合にはM&A仲介業者もなんとか成功させようと躍起になる可能性もあり、恣意的な情報が選択される危険性もあるため、経営者自身の目利きももちろん必要になります。
3:同業者、取引先などのコネクション
同業者や取引先のコネクションを使うのも、会社の売却先を検討する1つの方法といえます。特に付き合いの長い取引先などは、互いの情報をそれなりに持っている可能性が高くスムーズに話が進む可能性があります。
また、既に取引がある先なので、販売経路も拡張できる可能性が高いのもメリットといえます。
一方で、コネクションのみでは幅が狭く、そもそもM&Aを検討している先にたどり着くことができない可能性もあります。このため、まずは同業者や取引先に話を聞いてみて、同時並行で他の探し方を実践するのがよいでしょう。
4:金融機関に打診
実は金融機関にM&Aを打診することも可能です。特に、メガバンクになると持っている企業情報も多く、M&Aに特化した専門の部署を構えている銀行もあります。
何よりも、持っている情報が多いというのは強みですが、デメリットとしては、話をして興味をもってもらえなければなかなか話が進まないことがあります。
また、売却相談をしても、売却元にとっては都合が悪く、金融機関にとって都合が良い買い手を紹介される可能性もあります。したがって、金融機関に相談をする際は、担当者が信頼できる相手かを見定めた上で、慎重に相談をすることをおすすめします。
会社売買の方法と手順
会社の売買手段にはさまざまな方法があります。それぞれにメリットとデメリットがありますので、自社にとって最もよい手段を選ぶことが経営者には求められます。
本記事では6種類の会社売買の手段を紹介します。
1:事業譲渡
まずは事業譲渡です。事業譲渡とは、会社の株式は手元に残したまま、事業の一部ないし全てを売却する手段のことを指します。
事業譲渡は規模が大きければ大きいほど手続きの負担や税金の負担が大きくなるのがデメリットです。しかし、事業譲渡後に会社の売上が伸び、株価が上昇すれば、株式を保有している株主は株価値上がりの恩恵を受けることができます。このため、不採算事業の切り離しなどを実施する場合には、事業売却を実施するメリットがあります。
2:株式譲渡
株式譲渡は株式を売却することで、経営権を全て引き渡すM&Aの手法です。
手続きが事業売却と比較すると簡易であり、株式譲渡では経営者にはまとまったお金が入るためメリットといえます。
また、事業譲渡などと比べると、譲渡対価が株主に直接入ってくること、また、税金の負担が事業譲渡などと比べると小さくなるのがメリットといえます。
3:合併
合併には2種類の方法があります。1つの既存の会社にもう片方の会社をくっつける合併方法と、完全に新しい新設会社を立ち上げる方法です。
どちらを選ぶにせよ、手続きに大きな負担がかかってしまうのがデメリットです。
中小企業というより、大企業で使われる会社のM&A手法です。
4:会社分割
会社分割は事業譲渡と似ていますが、どこまでを譲渡するのかという点で大きく異なります。
事業譲渡では、会社の資産を細かく選択して売却するのに対し、会社分割では事業に係る資産を包括的に売却します。
包括的なのか個別的なのかが違いといえます。
5:株式交換・株式移転
株式交換・株式移転は今まで紹介してきたM&A手法を混ぜ合わせた方法になります。
株式交換が売却した株式の対価として、買収企業の株式を一部譲渡してもらうのに対し、株式移転では新会社を設立し、その新会社に売却予定の会社の株式を移転するスキームになります。
6:第三者割当増資
第三者割当増資とは、第三者に対して新しく発行した株式を割り当てるスキームのことを指します。基本的には取引先や銀行に対して新株を発行し、新たな株主として迎え入れます。
第三者割当増資は普通の増資と比較して、決まった相手に新株を発行できるというメリットはありますが、既存株主の希薄化が起こることがデメリットです。
また、新株発行の価格が企業価値よりも低い場合、株主総会で特別決議が必要になるケースがあります。また、この場合は既存株主からの批判を浴びる可能性もありますので、第三者割当増資を実施する際は、特に緻密なためデューディリジェンスを実施する必要があります。
M&A手続きの8つの流れ
実際に会社売却を検討する際には、売却の流れを把握することが重要です。
それでは、M&Aのためにはどういった手続きが必要になるのでしょうか。ここからは、M&Aの手続きを8つに分けて説明します。
1:会社売却の検討
まずは会社売却の検討をします。そもそも会社を売却する必要があるのか、どういった先が売却先として適切なのか、また、会社売却のスキームは何を選ぶのが最適なのかを検討します。
この際、M&A専門家にアドバイザリーを依頼すると、適切なアドバイスをもらえることがあります。この段階で、M&A専門家に依頼をしておくことをおすすめします。
2:売却先探し、交渉
売却方法とスキームが決定したら、売却先を探すフェーズに入ります。この際、既に説明したように、まずはマッチングサイトを利用するのか、それともM&A仲介会社を利用するのかなどの検討が必要になります。
自社にとって何が最適なのかは自社で検討することももちろん大切ですが、合わせてM&Aの専門家に相談をし、アドバイスをもらうことも検討するとよいでしょう。
3:秘密保持契約
売却先を検討する段階では、詳細な情報は開示されず、お互いが興味をもった段階で初めて会社名などの情報が開示されます。
M&Aに関する情報は非常にセンシティブで、社会的に与える影響も大きいため、具体的な話になった段階で必ず秘密保持契約を結ぶようにします。
秘密保持契約締結後に、具体的な資料などが開示され、交渉の成立に向けて両社が動いていく段階に移行します。
4:基本合意契約締結
売却先と買収先の間で話がまとまってきた段階で、基本合意契約を締結します。基本合意契約では、その時点での基本的な条件について内容のすり合わせを行います。
基本合意契約を締結することで、この後のデューディリジェンスの手続きなどを比較的スムーズに進めることができるようになりますので、非常に重要な手続きといえます。
一方で、基本合意契約では詳細の条件については法的効力を持たせないことが重要です。この後のデューディリジェンスの結果によっては再度内容のすり合わせが必要になる可能性があるからです。
5:デューディリジェンス
デューディリジェンスは会社売却の手続きの中で重要な手続きの1つです。M&Aの際には、財務・税務デューディリジェンスと法務デューディリジェンスを特に入念に行います。
買い手企業からすると、この際に簿外債務や偶発債務などが発覚する可能性があります。こうした債務の話は後からトラブルになる可能性があるので、デューディリジェンスの際には正確に質問に対して答えることが重要です。
特に調査項目が多岐にわたるため、売り手企業もヒアリングや現地調査、資料の提出などには協力することが必要です。
6:取締役会、株主総会
事業譲渡の場合には取締役会による決議、株主総会での特別決議が必要になる可能性があります。
事業譲渡の他にも、第三者割当増資では新株の発行価額によっては決議が必要になるケースがありますので、必要な手続きについて慎重に確認する必要があります。
この際、必ず専門家と相談し、抜け漏れがないかをチェックするようにしてください。
7:最終契約書の締結
最終契約書には企業の経営権を譲渡する重要な手続きです。この際、譲渡する株式が譲渡制限株式ではないかなど確認しなければならない項目は多岐に渡ります。
弁護士などとも相談し、入念にチェックを重ねる必要があります。
また、契約書については、買い手側の弁護士とも内容を確認し、交渉を行うようにしましょう。
8:クロージング
全ての手続きが滞りなく完了し、効力の発生日となるとM&Aの売却手続きは終了となります。
売り手側の手続きは終了し、今後は新経営者が経営を進めていくことになります。
まとめ
本記事では、後継者の不足に悩まされ、今後は会社を廃業しようと考えている経営者の方のために、会社売却という選択肢のご紹介をさせていただきました。
廃業することも確かに1つの選択肢ではありますが、会社売却をすることで、守られる雇用があります。また、愛着を持って育ててきた企業が、今後も成長を続けていく可能性もあります。
ただ廃業を検討するだけではなく、会社売却も今後の検討の1つに入れてみてください。