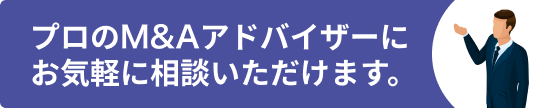【起業を目指す人向け】開業時の資金の調達方法を7つのカテゴリーに分けて紹介!
公開日:2021年8月31日 最終更新日:2023年1月23日
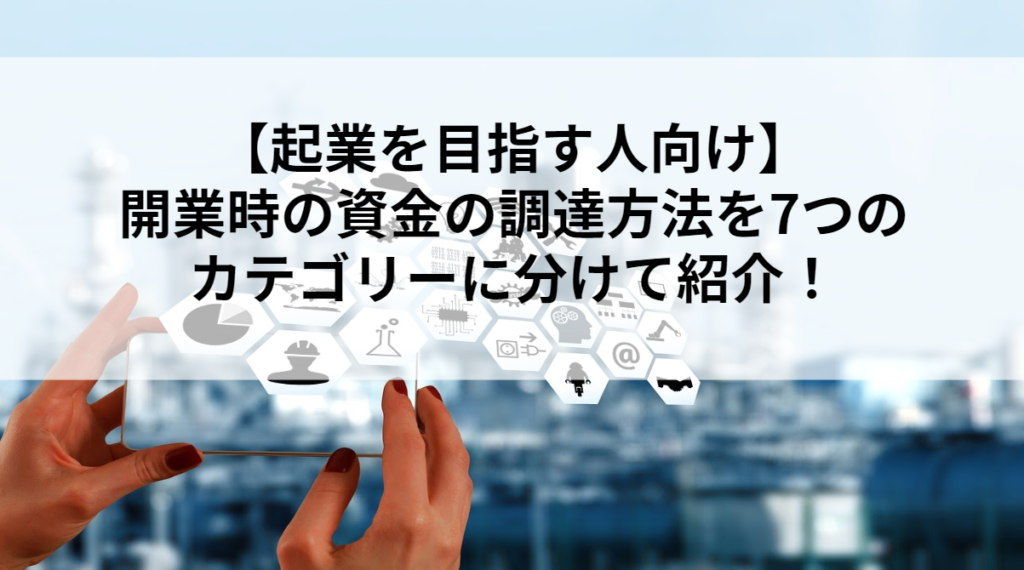
こちらの記事では、起業を目指す人向けに開業時に必要な資金の調達方法を紹介します。金融機関からの融資やクラウドファンディングの活用、返済の必要がない補助金や助成金を利用するなど、さまざまな選択肢があります。それぞれの特徴について見ていきます。
参考記事:資金調達とは?具体的な方法・種類からメリット・デメリットまでわかりやすく解説!
目次
開業時に利用できる資金調達方法を紹介
近年、行政や金融機関などが開業・創業のバックアップを推進しています。そのため、開業資金の調達手段は増えつつあります。
銀行や信用金庫などの金融機関からの借り入れのほか、クラウドファンディングを利用した調達、さらに返済の必要がない補助金・助成金などを受給できる可能性もあり、選択肢は多様です。
それぞれの特徴やメリット、デメリットについて説明していきます。
開業資金の調達方法7つ
開業資金を調達する際に一般的なのは、以下の7つの手段です。
- 自己資金で賄う
- 他人に出資してもらう
- 銀行などの金融機関からお金を借りる
- 日本政策金融公庫の融資制度を利用する
- 地方公共団体の制度融資を利用する
- 補助金・助成金を利用する
- 親族・知人からお金を借りる
参考:起業マニュアル 資金調達方法|独立行政法人中小企業基盤整備機構(J-Net21)
1:自己資金で賄う
まず一つ目は、自己資金で賄う方法が挙げられます。自己資金は返済の必要が無く、使用用途の制限なども無いため自由に使うことが出来ます。開業当初の経営が不安定な時期においては、返済の必要が無い資金を手元に蓄えておくことは特に重要です。
また、融資を申請する際にも、自己資金の金額に応じて融資金額の上限が定められるケースもあります。開業にあたって、できるだけ多くの自己資金を準備するに越したことはありません。
2:他人に出資してもらう
他人に出資してもらう方法があります。自己資金では足りない場合の選択肢となります。
特定の団体や個人から出資してもらうことで、金融機関の融資では対応できない案件などでも資金を集めることが可能です。出資者の種類や特徴はさまざまですので、それぞれ説明していきます。
ベンチャーキャピタル(VC)を利用する
まず、ベンチャーキャピタルから出資を受ける方法が挙げられます。ベンチャーキャピタルとはいわゆる「投資会社」であり、高成長が見込める未上場企業などに対して株式で出資を行います。投資会社ですので、最終的には株式上場等を通じて出資額以上の利益を得ることを目指します。
個人投資家(エンジェル投資家)に依頼する
続いて、個人投資家からの出資を受ける方法が挙げられます。創業間もない企業に出資する個人のことを「エンジェル投資家」と呼ぶることもあります。一般的には、会社経営者などの富裕層であることが多く、出資先のビジョンや創業者の将来性などを評価して出資するケースがあります。
クラウドファンディングを活用する
近年はクラウドファンディングで出資を募る方法もあります。インターネットを通じて、実現したい目標やビジョンを掲げ、一般大衆(クラウド)から支援者を募り、出資を得ます。
クラウドファンディングの中にも、ボランティア活動などと相性が良い「寄付型」や、リターンとしてモノやサービスを提供する「購入型」、起業家や企業が出資を受けるための「融資型」「株式投資型」「ファンド型」といったさまざまな種類が存在します。
出資を受ける場合のポイント
出資は融資と異なり、返済の義務がありません。これは大きなメリットと言えるでしょう。
一方で、出資の対価として株式を渡すことになりますが、このときに大量の株式を渡してしまうと経営権を握られてしまうケースがあります。
さらに、株式を発行するために会社法上の各種手続きを経る必要があります。また、出資者は当然、出資額以上のリターンを期待しています。専門家に相談しながら契約内容をしっかりと確認することをおすすめします。
3:銀行などの金融機関からお金を借りる
資金調達の方法として、銀行などの金融機関からお金を借りる方法があります。
VCから出資を受ける場合と比較して、金融機関からの融資は着金までのプロセスがシンプルかつ早いという特徴があります。また、株式を発行するわけではないので経営者の持分が希薄化する心配もありません。さらに、銀行に資金繰りに関する相談や、事業に関するアドバイスを求めることが出来るといったメリットもあります。
一方で、利息を含めた毎月の返済が必要です。また、融資を受ける際には審査を通過しないといけない点にも注意しましょう。
銀行にとっては融資先が滞りなく返済できるかどうかが重要であるため、創業初期に先行投資がかさみ黒字化まで時間がかかるようなビジネスモデルを採用している場合や、担保になるような資産がない場合には審査通過のハードルが上がると考えられます。
金融機関にもいくつかの種類がありますので、それぞれの特徴について見ていきましょう。
参考:起業マニュアル 金融機関の選び方|独立行政法人中小企業基盤整備機構(J-Net21)
・都市銀行
まず1つ目が都市銀行です。都市銀行の中でも規模の大きな銀行は「メガバンク」とも呼ばれ、誰もが名前を知っている銀行と言えます。全国各地に支店を展開しています。
一般的に、都市銀行は中小規模の創業融資に積極的であるとは言い難い状況で、主に預金取引で利用することが多くなります。とはいえ、事業計画の手堅さや担保となる資産の存在などを適切に訴求することで、創業間もない会社でも融資を受けられるケースもあります。
・地方銀行
地方銀行は、創業融資に積極的な銀行とそうでない銀行があるため、それぞれの取り組み姿勢などを確認する必要があります。積極的な銀行では、相談会やセミナーを積極的に開催しているケースがあります。
信用金庫・信用組合
信用金庫・信用組合は、銀行とは異なり、いずれも地域に根差した組織であるため、創業融資にも積極的なケースが多くあります。中小規模企業やその創業者がメインの顧客となるため、創業後の相談などにも乗ってもらえるケースがあります。
4:日本政策金融公庫の融資制度を利用する
日本政策金融公庫はいわゆる政府系金融機関と呼ばれる、財務省が所管する会社です。行政として創業を支援する姿勢を見せており、創業者向けのさまざまな融資制度が利用できます。
日本政策金融公庫は全国各地に支店があり、電話相談だけでなく窓口での相談も受け付けています。融資だけでなく、相談会やセミナーといった創業者支援のためのさまざまなイベントを実施しています。
5:地方公共団体の制度融資を利用する
5つ目は、地方公共団体の制度融資です。日本政策金融公庫は政府系の組織ですが、都道府県や市町村などの地方公共団体も融資を取り扱っています。
この制度融資は、地方公共団体の予算から直接資金を提供されるわけではなく、あくまで金融機関を通じた資金調達になります。資金の出所は金融機関で、行政がその機会、制度を提供している形になります。
そのため、行政だけでなく金融機関との手続きも必要となり、融資に時間がかかってしまう点は注意が必要です。
6:補助金・助成金を利用する
返済の必要がないという点は補助金・助成金の大きなメリットです。
補助金・助成金には要件が定められており目的に沿った形でないと利用できないケースがあります。また、応募者が多数の場合はコンペとなります。
デメリットとしては、後払いである点が挙げられます。取組み結果を報告した後での受け取りとなるため、資金を受け取るまでに時間がかかります。また、受け取った補助金・助成金は会計上の営業外収益に該当するため、法人税額計算上は課税対象となることも注意が必要です。
参考:起業マニュアル 補助金・助成金の活用|独立行政法人中小企業基盤整備機構(J-Net21)
地方創生起業支援事業による起業支援金(東京圏の一部を除く全国)
補助金・助成金の一例として、地方創生起業支援事業による起業支援金が挙げられます。東京、埼玉、千葉、神奈川以外の都道府県で利用できます。東京圏でも一部地域では利用可能です。
内閣官房・内閣府総合サイトに記載されている「地方創生起業支援事業の概要」には、起業をする上で最大200万円の事業費への助成金を受けることができます。
出典:地方創生起業支援事業の概要|内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生
東京都中小企業振興公社の創業助成金(東京都)
東京では、東京都中小企業振興公社の創業助成金が利用できます。対象は、都内で創業を予定されている方や創業後5年未満の中小企業者で、一定の条件を満たす方です。
助成対象は賃借料、備品購入費、産業財産権出願・導入費、広告費、従業員人件費、専門家指導費となっています。
7:親族・知人からお金を借りる
自身のコネクションやネットワークを利用することになります。
創業前のような実績が無い状況でも、親族や知人であれば資金を貸してくれる可能性は高いです。
一方で、親しい間柄であるがゆえに、契約内容の詳細を決めなかったり、書面に残さないといったケースも見受けられます。事業が成長した際や、逆にうまくいかず撤退する際のトラブルの原因になり得るため、注意が必要です。
万が一に備えて共済に入る
小規模企業の経営者や役員、個人事業主といった方向けに小規模企業共済について説明します。
共済の場合、加入後は月々の掛金を支払い、退職時や廃業時に共済金として受け取れます。掛金が課税対象所得から控除できることも大きなメリットです。
また、小規模企業共済加入者は、掛金の範囲内で事業資金の借入が可能です。何らかの原因で経営が大きく傾いたタイミングや、傷病災害時などはもちろん、開業時や事業承継のタイミングなどでも借り入れが可能です。借入までの期間も非常に短く、金利も低く借りられるため、非常に便利な制度です。
参考:小規模企業共済 制度の概要|独立行政法人 中小企業基盤整備機構
まとめ
近時、行政や金融機関が中心となって社会全体で創業をバックアップする体制が整いつつあります。
自己資金だけで創業ができない場合でも、少しでも有利な条件で資金調達を目指す必要があります。さまざまな資金調達方法の特徴を理解して、ご自身にあった方法を選んでいきましょう。
M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」では、会社を買いたい企業が、欲しい企業の要件を記事として公開中です。買い手となる企業を手軽に探すことができるほか、M&Aアドバイザーに会社売却について無料相談することも可能です。お気軽にご相談ください。