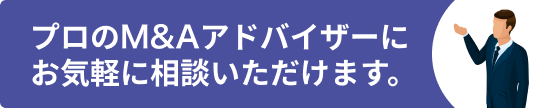M&Aの成功に重要な役割を果たすDDとは?|その目的とプロセスまた注意点も
公開日:2021年11月30日 最終更新日:2022年11月17日

M&Aにおけるデューデリジェンスの概要と目的を解説します。デューデリジェンスの種類は10項目に分けられており、それぞれ意味がことなります。
今回は、デューデリジェンスの種類とM&Aのデューデリジェンスの実施の手順・押さえるべき3つのポイントを紹介します。
目次
M&Aにおけるデューデリジェンスとは
デューデリジェンスとは、投資を実施するにあたって投資対象について詳細に調査することを指します。「デューデリ」や「DD」などと略されます。
M&Aにおけるデューデリジェンスは、買収対象企業の経営環境や事業内容などを調査し、財務状況・収益力や法務上の問題点、リスクなどについて調査し、正確な企業経営の実態を把握するために実施されます。
M&A取引の意思決定において、買収対象企業に対する事前のデューデリジェンスは欠かすことができません。この記事ではM&Aにおけるデューデリジェンスの目的とプロセスについてわかりやすく解説します。
M&Aにおけるデューデリジェンスの意義
M&Aにおけるデューデリジェンスは、買い手がM&A対象の実態を知るために、財務や税務、労務など企業全般の数字や経営環境などを把握するステップです。
実行の可否決定、対価額の決定、実行後の運営戦略に役立てるための情報収集作業といえるでしょう。M&Aを成功させるために、デューデリジェンスは避けて通ることのできない重要なプロセスとなります。
デューデリジェンスの5つの目的
デューデリジェンスには主に5つの目的があります。
1.M&Aのストラクチャーの確認
2.より広範な情報に基づいた企業価値評価
3.M&A戦略に関する説明責任を果たすための情報収集
4.新たに判明したリスク等の最終契約内容への反映
5.PMIおよびその後の経営のための情報収集
上記について詳しく説明していきます。
1:M&Aのストラクチャーの確認
デューデリジェンスの目的の1つ目は、予定していたストラクチャーを実行して問題ないのかを確認することです。今検討されているM&Aの手順・手法の可否を判断する材料となります。より良いストラクチャーがあるという可能性も含めて、最適なM&Aの選択のためにデューデリジェンスが必要なのです。
2:より広範な情報に基づいた企業価値評価
デューデリジェンスの目的には、企業価値の正確な評価が含まれます。デューデリジェンスによって、公に明らかにされている情報だけではなく、財務諸表に表示されていない簿外債務なども含めたより広範囲の情報が得られます。買い手側企業は正確な企業価値評価によって、適正な買収価格を設定し、高値掴みのリスクを軽減できるでしょう。
3: M&A戦略に関する説明責任を果たすための情報収集
デューデリジェンスにより得られた情報に基づいて、自社の戦略に必要なM&Aであることを利害関係者に説明できます。対象の会社が買い手企業の戦略に貢献することを説明する根拠を得るのです。
特に近年、経営者の説明責任がより強く問われる傾向があります。M&Aの合理性・適合性について、株主をはじめとする利害関係者に説明するために、デューデリジェンスを行う必要があります。
4:新たに判明したリスク等の最終契約内容への反映
デューデリジェンスの目的の4つ目は、リスクの洗い出しです。デューデリジェンスを行うことで今まで見えてこなかった問題が表面化することがあります。買い手側が負担したくないリスクは、最終契約内容でそれらのリスクを切り離すという対応ができます。
また、買収価格の調整や、最終契約に改善事項を盛り込むなどの対応が取られる場合があります。最終契約に至る前にあらかじめリスクを把握しておき、対応策をとるためにデューデリジェンスが必要なのです。
5:PMIおよびその後の経営のための情報収集
デューデリジェンスのもう1つの大きな目的は、PMIを円滑に進めることです。PMIとはM&A成立後の統合プロセスのことで、Post Merger Integration(ポスト・マージャー・インテグレーション)の略です。M&A成立後に、売り手側・買い手側の双方の経営戦略や販売体制、サプライチェーン、人材、システムなどを効果的に統合する過程がPMIとなります。
M&Aのシナジー効果を早期に、また確実に実現させるためには、PMIがスムーズに行われる必要があります。デューデリジェンスでは、売り手側企業の管理体制や、人材の状況、システム運用の実態などの生の情報を入手することができ、スムーズなPMIに資する情報を獲得できます。
また、想定される統合リスクを十分に洗い出し、PMIの過程で起こりうる問題への対処をあらかじめ検討しておけるという点にも、デューデリジェンスの意義があります。
デューデリジェンスの種類10項目
デューデリジェンスには、その調査の視点・切り口によって、下記の主に10種類があります。
1.事業デューデリジェンス
2.財務デューデリジェンス
3.税務デューデリジェンス
4.法務デューデリジェンス
5.人事デューデリジェンス
6.ITデューデリジェンス
7.環境デューデリジェンス
8.知的財産デューデリジェンス
9.顧客デューデリジェンス
10.不動産デューデリジェンス
必ずしもこれらのデューデリジェンスをすべて実施する必要性はありません。M&Aの状況に応じて必要なデューデリジェンスが選択され、優先順位をつけて実施されます。
ここからは、これらの10種類のデューデリジェンスの内容を1つずつ解説します。
1:事業デューデリジェンス
事業デューデリジェンスとは、市場全体を鑑みる包括的な視点での調査です。買収対象会社の事業の市場推移や、事業の将来性などが調査されます。
また、競合他社の顔ぶれ、ビジネスモデル、シェア動向が調査され、売り手側企業の業界内でのポジショニングが調査されます。さらに、新規参入企業の動向、成長要因の持続性の見積もりなどから、買収される企業の持続性が分析される場合もあるでしょう。
これらの情報を得た買い手側企業は、M&A対象の事業の将来性を見極め、経営計画の実現やM&Aの目的・戦略と適合しているかを総合的に判断することになります。
2:財務デューデリジェンス
財務デューデリジェンスとは、財務的観点からの調査です。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの主な財務諸表をベースに、対象企業の財政状態について調査することが財務デューデリジェンスのメインとなります。
また、正常収益力分析、簿外債務の有無や資金繰りなどの財務状態についても詳細に調査します。買収後の不正リスクとなりうる、グレーな取引や恣意的な経理処理がないかも調査される場合があります。
財務デューデリジェンスによって、正確な収益力・キャッシュフローなどの基礎情報を得て、将来期待できる収益水準のレベルや、債務が妥当な範囲内かなどを確認します。財務面から総合的にM&Aの意思決定に資する情報を収集するのが、財務デューデリジェンスなのです。
3:税務デューデリジェンス
税務デューデリジェンスでは、税務リスクについて過去の税務申告書や帳簿がチェックされます。もし被買収企業に未払税金があった場合、M&A後に買収側の企業に支払義務が生じてしまいます。
申告書の記載内容の不備や、届出の漏れ等があれば、M&A成立後に追徴課税が発生します。こういったリスクを洗い出すための調査が税務デューデリジェンスです。
また、M&A後に税務調査が入った場合、調査での指摘事項に対応する主体は買収側の企業となる場合がほとんどです。そのため、適正な申告、納税がなされているかを調査する税務デューデリジェンスは買い手側企業にとって重要なものとなります。
4:法務デューデリジェンス
法務デューデリジェンスとは、M&A対象企業とその事業の法務を対象とした調査です。会社の沿革・商業登記・株主情報・許認可などの基本情報から、過去の訴訟、現在抱えている係争案件などを調査します。また訴訟リスクのある長期の滞留債権債務の有無についても調査されます。
M&Aが成立すると、被買収会社が顧客や取引先、従業員と結んだ契約を引き継ぐ場合がほとんどです。法的リスクがあると、訴訟が起きた際に莫大な時間とコストが使われることになります。また企業への評判や株価にも悪影響を与えるため、想定される法務上のリスクを把握することが必要不可欠となります。
5:人事デューデリジェンス
人事デューデリジェンスは人材に焦点を当てた調査です。調査対象には人事制度や人件費だけでなく、マネジメント体制、人事システムや労使関係も含まれます。これらの情報は、M&A後の両社の人事制度や労働条件の統合の際に必要な情報です。
また、買収によって労働条件や人事制度が変わることが、買収される企業の従業員にとってどんな影響を与えるかを確認する意味もあります。
たとえば、被買収会社の優秀な社員が、買収後の待遇などに不満を持ち、辞めてしまう可能性があるかもしれません。このような人事面のリスクを想定した上で、調査に基づいたM&Aの条件のすり合わせが行われます。
6:ITデューデリジェンス
ITデューデリジェンスとは、対象企業の情報管理システムを調査、分析するデューデリジェンスです。売り手側企業の用いているシステムが買収側の使用しているシステムと統合できるのか、それとも完全なリプレイスが必要になるのか、などが調査されます。
また、システム統合にかかる作業量やコストを考慮するとともに、経営統合後のシステム運用の方法を検討するための資料としても活用できるでしょう。
メールやチャットに用いるコミュニケーションツール、勤怠管理システム、会計システムなどは、ほとんどのM&Aにおいて統合方法の検討が必要です。また、IT企業や金融機関など、情報システムが経営上の重要な資源になっている場合には、ITデューデリジェンスはより重要な調査となるでしょう。
この場合、メンテナンスや統合に関わる投資などが考慮され、買収価額に反映される場合もあります。
7:環境デューデリジェンス
環境デューデリジェンスは、対象企業に環境関係の問題がないか調査するものです。買収対象の企業が保有する不動産に関連した土壌・地下水汚染のリスク調査がメインとなります。
ほかにもアスベストや、排出ガス、オゾン層破壊物質、排水水質、騒音・振動、産業廃棄物、危険物貯蔵施設などが調査対象となることがあります。これらが環境規制に準拠して適正に処理されているかを検証することで、将来的に罰則を受けるリスクを排除できるのです。
もし、環境問題への対策が行われておらず、追加の施策や工事などが必要であれば、そのコストを見積もります。その結果によってはM&Aスキームの変更や、買収価額への織り込みが必要な場合もあります。
また、昨今のSDGsを推進するトレンドを受けて、サプライチェーンも含めた企業活動の環境に与える影響を把握することは、経営統合後の企業グループの社会的責任(CSR)遂行にも有効な調査といえます。
8:知的財産デューデリジェンス
知的財産デューデリジェンスでは、対象企業の持つ知的財産の調査を行ないます。対象企業が保有する著作権や特許権の価値とリスクの調査、分析が行われます。この調査には現在使っている技術が第三者の知的財産を侵害していないかの確認が含まれる場合もあるでしょう。
この場合、追加の技術使用料の発生のリスクを見積もることになります。また、対象企業が保有する知的財産を活用した商品開発のアイデアや、M&A後のビジネス展開のシミュレーションにも有効な調査です。
9:顧客デューデリジェンス
顧客デューデリジェンスとは、譲渡企業の顧客についての調査です。買収対象企業の既存顧客の調査を行い、反社会的勢力の排除やマネーロンダリングへ加担するリスクを排除するという意義があります。
10:不動産デューデリジェンス
不動産デューデリジェンスでは、譲渡企業の有する不動産の分析・調査を行ないます。買収対象企業の資産価値を正確に評価するためのもので、専門の不動産鑑定士による調査・分析が不可欠です。
不動産の資産価値は、周囲の環境や地価によって大きく変動することがあり、結果によっては買取価格に影響を与えることがあります。また、不動産によって収益を得ている企業のM&Aにおいては、不動産の収益性の正確な見積もりが必要です。
デューデリジェンスの流れ
デューデリジェンスの大きな流れとしては、まず買い手側の企業が公認会計士やコンサルティング会社などの専門家にデューデリジェンスを依頼します。
依頼された専門家はDDチームを組んで、譲渡企業を訪問します。そして現地で会計帳簿の閲覧や、経営者や関連部門へのヒアリングを行い、報告書をまとめます。
具体的なプロセスとして下記のような段階を踏むのが一般的です。
- 基礎資料の入手、案件概要の把握
- ミーティング、調査範囲のすり合わせ
- 事前調査・分析
- 調査範囲・手続きの決定
- 依頼資料リストの送付
- 資料の閲覧・分析
- 質疑応答・インタビュー
- 報告書の作成
- 最終報告
デューデリジェンスのポイント
デューデリジェンスを実施するにあたっては、次の3つの点が重要なポイントとなります。
・タイミング
・事前の計画
・DDを外部の専門家に依頼すること
ここからはこの3つのポイントについて解説します。
実施のタイミング
デューデリジェンスを実施するタイミングは、基本合意契約が締結された後、最終条件交渉に移る前に行われるのが一般的でしょう。基本合意前では、売り手側企業は譲受企業(買い手)を絞り込めていない可能性があります。
このタイミングではまだ、M&Aが白紙に戻る可能性があり、デューデリジェンスの費用と時間を無駄にする恐れがあります。
基本合意契約に至っていれば、売り手側企業はM&Aにおおむね納得しているわけですから、デューデリジェンスに協力を得られるでしょう。しかし遅すぎると、事業環境や売り手側企業の状況が変わってしまうことがあります。
早すぎず遅すぎず、適切なタイミングでデューデリジェンスを実施することが重要です。
事前に計画を立てポイントを絞る
これまで述べてきた通り、デューデリジェンスには多くの種類があり、調査対象も多岐にわたります。目的が曖昧なまま闇雲にデューデリジェンスに取り掛かってしまうと、費用や時間の浪費につながるばかりか、必要な情報にたどり着けないこともあります。
限られた期間内で、有効な情報を入手するために、事前に周辺情報を下調べし、実施すべきデューデリジェンスの種類と優先順位をつけ、計画的に実施することがポイントです。
優秀な外部アドバイザーを使う
デューデリジェンスでは、外部の優秀なアドバイザーを活用することがポイントとなります。第三者である外部のアドバイザーから客観的な立場で調査をしてもらうことで、信頼できる調査結果を得ることができます。
M&Aのデューデリジェンスを専門的に行うアドバイザーに依頼をすると、各分野の専門的知識を活かした課題の把握だけではなく、経営統合後の事業展開にも有効な調査やアドバイスを期待できます。
まとめ
M&Aにおけるデューデリジェンスには相手の企業をよく知り、M&A後に引き受けるリスクを把握するという目的があります。また、PMIをスムーズに進めるために有効な情報を得られるでしょう。
デューデリジェンスには多くの種類とプロセスがありますが、必要な調査と優先順位を決め、外部アドバイザーを有効活用し、計画的に実施することで、効果的なデューデリジェンスを行うことができます。M&Aを成功させるためには、十分なデューデリジェンスを行うことが必要不可欠となります。
M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」では、会社を買いたい企業が、欲しい企業の要件を記事として公開中です。買い手となる企業を手軽に探すことができるほか、M&Aアドバイザーに会社売却について無料相談することも可能です。お気軽にご相談ください。