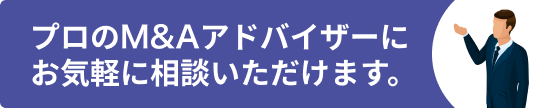デューデリジェンス(DD)の目的とは?買い手企業が押さえるべきDD11種の内容と手順を解説
公開日:2021年8月31日 最終更新日:2022年11月18日

本記事では、M&A(Merger And Acquisition・企業の合併と買収)の手続きに欠かすことのできないデューデリジェンス(Due Diligence・DD)について説明しています。
デューデリジェンスの種類から実際の手続き方法までをわかりやすく解説していますので、今後M&Aを検討している経営者の方はぜひ参考にしてください。
デューデリジェンスとは?
デューデリジェンスとは、M&Aや組織再編を実施する際に必要な手続きです。
買収を検討している企業の経営状況・事業内容について調査し、法務の問題点、財務面から見たリスクの有無を検証することで、数字だけでは見えない企業の実態を把握することを目的としています。
デューデリジェンスを怠ると、企業を合併・買収した後に大きなリスクが生じる可能性があります。
参考記事:
・M&Aのデューデリジェンスとは?7種のDDで売り手企業に求められる準備と注意点
・M&Aに必要なDDとは?種類や手順・注意点についても解説
デューデリジェンスを行う目的
デューデリジェンスは、企業価値の再検討とリスクの把握のために行います。
企業には、数字だけでは見えないリスクがいくつも隠れています。例えば、損益計算書を見ると、どれだけの利益が発生しているのかわかりますが、残業代が従業員に対してしっかりと払われているかはわかりません。
もしかすると、買収後に買収以前の残業代を従業員に請求される可能性もあります。こうした予期せぬ支出(負債)を簿外債務と呼びます。デューデリジェンスを怠ると、こうしたリスクに気付けないケースがあります。
リスクを極力排除するために財務、法務などの面から専門家たちがリスクを計測します。少し手間がかかりますが、買い手企業を守るために欠かせないのがデューデリジェンスです。
基本的なデューデリジェンスの種類
ここでは、実際の現場で利用されるデューデリジェンスの種類について説明します。以下7つの基本的なデューデリジェンスと、その他やや細かなデューデリジェンスを解説します。
(1)ファイナンシャルデューデリジェンス(財務デューデリジェンス)
1つ目はファイナンシャルデューデリジェンスです。ファイナンシャルデューデリジェンスとは、財務デューデリジェンスとも呼ばれます。
ファイナンシャルデューデリジェンスは、デューデリジェンスの中で特に重要だといわれています。誤った経理処理がされていないか、もしくは不正取引が行われていないかを確認します。
ファイナンシャルデューデリジェンスを詳しく確認することで、この先も買収先企業は利益を出し続けることは可能か、借入が膨大ではないかを判断できます。
企業価値算定の是非を問う根幹の調査にもなりますので、M&Aの検討の際には欠かすことができません。
(2)ビジネスデューデリジェンス
2つ目のビジネスデューデリジェンスでは、事業のリスクを洗い出します。扱っている製品、商品などに問題はないか、取引先によりシナジー効果が見込めるかを検討します。
一歩踏み込んで、事業のビジネスモデルから営業、マーケティングの方法まで精査することもあります。ビジネスデューデリジェンスにより、買収後に予定しているシナジー効果が見込めるか、どの分野で共同開発が可能かを洗い出すことが可能です。
ビジネスデューデリジェンスでは、SWOT分析などのフレームワークを利用して会社を分析することもあります。どのフレームワークを利用して事業の分析をするかは、各専門家によって分かれます。
(3)人事デューデリジェンス
3つ目の人事デューデリジェンスは、特にPMI(Post Merger Integration)において大切になる手続きです。PMIは、会社を統合する際に重要な概念であり、M&Aを有効に利用するために、合併した後の制度を整えることを指します。
企業の元になるのは、ヒト、モノ、カネです。その中でも人事評価に関わるのが、人事デューデリジェンスです。M&A後の会社を実的に動かすのは人なので、人事デューデリジェンスを実施し、制度のリスクを洗い出しておかないと社員のモチベーションに関わります。
どれほど机上のシナジーを見込んでいても、肝心な従業員がついてこなければ会社は機能しません。このため、人事デューデリジェンスも注意して実施するようにしましょう。
(4)ITデューデリジェンス
4つ目のITデューデリジェンスで実施するのは、管理システムの確認と精査です。顧客管理システム、販売管理システム、給与管理システム、会計システムなど、さまざまなシステムが絡み合って事業は成り立ちます。
合わせて、インターネットシステムも社内にサーバーを置いているのか、それとも仮想サーバーを走らせているのかで取扱いが変わります。
どのシステムを利用しているかで、その後のシステム統合の難易度が変わってきます。このため、買収会社は譲受会社のシステムの精査を実施することが非常に大切です。
(5)リーガルデューデリジェンス(法務デューデリジェンス)
リーガルデューデリジェンスは法務デューデリジェンスとも呼ばれます。
リーガルデューデリジェンスで明らかにするのは、M&A後に法的な問題が生じる可能性があるかです。例えば、許認可を例にとっても、M&Aによっては許認可を再度取得する必要がありますし、届け出をするだけで済むものもあります。
この他にも、例えば買収予定の企業が損害賠償の訴訟を受けているケースでは、その後さらなる賠償金が要求されることはないかを精査する必要があります。
このように、法的に問題がある手続きが生じないかを確認するのがリーガルデューデリジェンスの役割です。
(6)税務デューデリジェンス
6つ目の税務デューデリジェンスで確認するのは、税務からみた買収先企業のリスクです。
決算書を確認する点では、財務デューデリジェンスとも似ていますが、税務デューデリジェンスでは別表の法人税の損金、益金などの税務関係を詳細に確認します。
繰越欠損金の算出の仕方に問題はないか、法人税などに脱税の可能性がないかなども総合的に判断するのが税務デューデリジェンスです。
企業・事業を買収後のリスクは買い手が引き受けることになるので、税務デューデリジェンスの精査も非常に重要です。
(7)デューデリジェンスその他の種類
主なデューデリジェンスについて解説しましたが、この他にも状況に応じて必要になるデューデリジェンスがあります。以下の項目で、それぞれ解説をします。
・知的財産デューデリジェンス
知的財産デューデリジェンスとは、知的財産と呼ばれる目に見えない財産価値やリスクの算定をすることをいいます。ITや情報産業、オープンイノベーションが成長していく中で、知的財産デューデリジェンスの重要性が増してきています。
知的財産デューデリジェンスの重要性は、その価値判断の難しさにあります。客観的な判断が難しいため、売り手が提示している金額が果たして適正価格なのかどうかがわからないケースがあります。
この際に、自社のみで判断するよりも、知的財産デューデリジェンスを専門家に依頼するケースが少しずつ増えています。
・顧客デューデリジェンス
顧客デューデリジェンスとは、買収予定の会社が抱える顧客のリスクの算定をすることを言います。
顧客デューデリジェンスは、マネーロンダリングの規制が引き締められる中で、その重要性を増してきました。顧客が暴力団関係者ではないか、反社会勢力の関係者でないかを確認することは今後もより一層求められます。
買収企業の顧客を理解するためのプロセスとして、顧客デューデリジェンスは実施されます。
・不動産デューデリジェンス
不動産デューデリジェンスとは、特に売り手から土地や建物などの不動産を取得する際に実施されるデューデリジェンスです。例えば、株式譲渡などで会社を買い取る場合に、買い手の資産に不動産が入っている場合は不動産デューデリジェンスが必要です。
不動産デューデリジェンスでは、不動産の経済的側面、物理的側面、法的側面からそれぞれ問題がないかを確認します。
不動産の譲渡に関しては、売り手による重要事項説明が必須ですが、重要事項説明から得られる情報は少ないのでこうした手続きが必要です。
・技術デューデリジェンス
技術デューデリジェンスとは、製品や現在開発している製品技術の価値を算定することです。
技術デューデリジェンスを実施することで、技術製品の価値の妥当性についての算定が可能です。例えば、ソフトウェアやハードウェア、開発中のアプリケーションなどに適正価格を付けるのは難しい側面があります。
この際、技術デューデリジェンスを利用することで、客観性を増すことができます。
・環境デューデリジェンス
環境デューデリジェンスとは、企業が環境の土壌汚染などに意図せず関わってしまっていないかを洗い出すことをいいます。
近頃では、環境保護や社会貢献などSDGs(持続可能な開発目標)の観点から企業経営に関わることの重要性が増しており、環境リスクを意識した企業経営が、ステークホルダーに求められつつあります。
環境面からのリスクを把握することで、予期せぬ訴訟や賠償金などを認識し、対応することできるので、環境デューデリジェンスを実施する企業もあります。
デューデリジェンスの手順
実際にM&Aを検討する際に、デューデリジェンスはどのように実施すればいいのでしょうか。ここからはデューデリジェンスを実施する際のスケジュールとポイントについて、それぞれわかりやすく解説します。
実施方針の決定
まずは実施方針の決定をします。
買い手内部で決定すべきなのは、期間、外部に委託するデューデリジェンスの分野、デューデリジェンスにかけられる予算です。
どこまでデューデリジェンスに費用をかけられるかは企業によって変わるので、自社で実施できるものは内製化するのも手です。全てを弁護士や会計士などに任せる必要はありません。
初期情報の確認
デューデリジェンスを実施する際には、売り手企業から必要書類をもらう必要があります。
具体例として、決算書、税務申告書、定款、株主名簿、取締役会の議事録が代表例で挙げられます。他にも、月次売上、設備投資、資金繰り表など、必要とされる資料はすべて徴求します。
その後、これらの資料と別途専門家から依頼される資料も、売り手企業から徴求します。
ミーティングの開催
M&Aの買い手(デューデリジェンス実施依頼側)と専門家の間でデューデリジェンスの注意点やポイントなどの認識を共有しておきます。この際、どれくらいの時間で依頼するかは明確に打ち合わせしておくようにしましょう。
今何をやっているのかが伝わらないとと、売り手も自社は売れないのではないかと心配してしまうケースがあります。
請求する資料リストの作成
専門家との打ち合わせや事前準備で決めた資料をまとめ、資料リストを作成します。その後、譲渡企業より資料を徴求します。
この際、譲渡企業には、追加で資料を追求する旨を伝えておくとその後のトラブルが少ないです。
開示資料の確認
受領した開示資料を確認します。この際、依頼した資料が揃っているかを確認します。万が一資料が揃っていない場合は、再度申請をし、開示資料を送ってもらうようにします。
合わせて、外部専門家が受領した開示資料も整理、分析する必要があります。全てを専門家に丸投げするのではなく、自社でも確認しておくことが必要です。
開示資料を確認する際のポイントは、シナジー効果が真に見込めるのか、リスクがないのかの検証をすることです。
インタビューやQ&Aシートを用いた質疑応答
受領した資料を確認するだけでは売り手会社のすべてを理解することはできないので、マネジメントインタビューを実施します。
マネジメントインタビューは、売り手経営者との面談形式で、経営者の人となりなど、書類では見えない部分を確認する目的で行います。マネジメントインタビューは買い手、買い手側の弁護士などが実施します。
この際、質問事項をQ&A形式でまとめておくとお互いに負担がかかりませんので、必須質問事項と任意事項に分け準備をしておくことをおすすめします。
中間報告と追加資料の請求
中間報告を設けることで、重要な事項を早めに共有するなど、デューデリジェンスの結果を踏まえて売り手との交渉ができます。
このため、最終まで結果をブラックボックス化するのではなく、自社で共有できる中間報告を設けるのが良いです。
また、中間報告で新たに確認しなければならない事項が発生した場合には、追加で資料請求を行います。
最終報告
すべてのデューデリジェンスが終了すると、最終的に外部専門家は、買い手企業にデューデリジェンスの結果を報告します。これをデューデリジェンス報告書、デューデリジェンスレポートと呼びます。
結果の検討・活用
最終報告の結果を踏まえて、買い手は引き続き交渉を行うのか否かを決定します。特に、簿外債務などの、企業価値算定に関わる重要事項が発生した場合には、買い手は値下げ材料として売り手と交渉できるようになります。
まとめ
本記事ではデューデリジェンスの種類と、実際の手続きの方法を解説しました。デューデリジェンスは円滑なM&Aを実現させるためには欠かすことができません。
今後M&Aを検討されている場合は、デューデリジェンスを実施する必要性を認識しておきましょう。
M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」では、会社を買いたい企業が、欲しい企業の要件を記事として公開中です。買い手となる企業を手軽に探すことができるほか、M&Aアドバイザーに会社売却について無料相談することも可能です。お気軽にご相談ください。