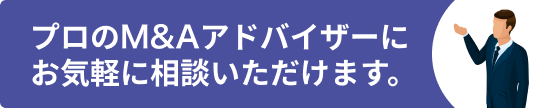会社売却時の債務の取り扱いは?M&Aの手法と債権者保護手続きの要否
公開日:2021年12月17日 最終更新日:2022年11月18日

M&Aでは、債権者がその会社の決定に対して異議を述べることができることがあります。この異議を述べる機会を保障することを債権者保護手続きといいますが、M&Aの手法によってその要否が異なります。ここでは債権者保護手続きの内容とその要否について説明します。
目次
会社売却時の債権者保護手続き
ある一定の会社の経営権や事業譲渡をする時に、事業やその事業に関連する資産を廉価で売却してしまったら、それを引き当てに取引をしていた債権者にも影響がでる場合があります。
そこでM&Aの際に、債権者の利益を保護するため、債権者がその会社の決定に対して異議を述べることがあります。この異議を述べる機会を保障する手続きが債権者保護手続きです。
ここではM&Aにおける債権者保護手続きの要否とその内容を説明します。
債権者保護手続きとは
会社債権者に影響を与える恐れのあるM&Aを行う場合、会社は債権者がそのM&Aに異議を述べられる機会を確保することが会社法上、義務づけられています。この手続きを債権者保護手続きといいます。
かかる手続きを経なければならない会社は、事前に官報に公告し、知れている債権者には各別に催告し、債権者が異議を述べることが可能な一定の期間(1カ月)を確保しなければなりません。
債権者が定められた期間内に異議を述べた場合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
M&Aの手法6つと債権者保護手続きの要否
M&Aの手法によって債権者保護続きの要否が異なることがあります。ここでは、事業譲渡、株式譲渡、株式交換、株式移転、会社分割、合併という6つのM&Aの手法それぞれについて、債権者保護手続きの要否とその理由について説明します。
1:事業譲渡
事業譲渡の場合は、債権者保護手続きの定めがありません。事業譲渡は取引行為という性質の行為であるため、事業に関する権利義務関係の移転について、各債権者から個別に承諾を得る必要があるからです。
その一方で、移転しない権利義務関係の債権者からすれば、債務者の事業構造が変わり、その債務者の財務状況に影響が出る可能性があるため、不利益を被る可能性があります。
そこで、例えば債務超過の企業が対象事業を低廉に事業譲渡するなどの場合には、詐害行為取消権を行使して事業譲渡を取り消すことができる場合があります。
2:株式譲渡
株式譲渡の場合においても、債権者保護手続きの定めはありません。これは、事業譲渡のように事業に紐づく権利義務関係が移転する場合と異なって、単なる株式という財産の権利者が移転する取引に過ぎないからです。
3:株式交換
株式交換の場合、債権者保護手続きは原則不要になります。株式交換は、完全親会社となる会社が、完全子会社となる会社の株式の全部を取得するだけであり、合併のように会社自体が消滅したり、会社分割のように事業に関する権利義務関係の移転がないためです。
ただし、たとえば、完全子会社にて発行していた新株予約権が新株予約権付社債である場合は債権者保護手続きを経る必要があります。
また、完全親会社において、完全子会社の株主に対して交付する金銭等が完全親会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの以外の場合等は、債権者保護手続きを経る必要がありますので注意が必要です。
4:株式移転
株式移転の場合は、株式交換の場合とほぼ同じです。株式移転は、新たに設立する会社に完全子会社化となる会社の株式の全部を取得させることであり、株式交換と同様に、会社自体が消滅したり、事業に関する権利義務関係が移転したりすることがないからです。
5:会社分割
会社分割では、債権者保護手続きが必要になります。たとえば、優良事業と不採算事業を切り分けて、不採算事業のみを残して優良事業だけ切り離すと、会社債権者は債権の回収ができなくなる恐れがでるからです。
異議を述べられる債権者は会社法によって定められており、たとえば、吸収分割のようなケースにおいては、吸収分割後に、債権者が吸収分割会社(売却側)に対して債務の履行を請求することができない債権者等がそれに当たります。
6:合併
合併の場合においても、債権者保護手続きが必要になります。
たとえば吸収合併のケースにおいて、消滅会社の債権者からしてみれば、契約の相手方が消滅会社(売却側)から存続会社(買収側)に移行することになるため、契約当初の債務者の事業や財務の状況が変わることになるからです。
債権者保護手続きの流れ
会社法に定められている要件に該当する場合、売り手は債権者保護手続きを経る必要があります。吸収分割における分割会社(売却側)を例にとれば、以下のような手続きで進めます。
①分割会社は、官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。
②公告等をする事項は、以下となります。
- 吸収分割等をする旨
- 吸収分割承継会社の商号及び住所
- 株式会社に限って、吸収分割会社及び吸収分割承継会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
- 債権者が一定の期間内に異議を述べることができること(ただし、一定の期間は、1か月を下回ることはできません。)
ただし、定款で債権者保護手続きの公告を日刊紙又は電子公告で行うことができる旨を定めた場合は、各別の催告は不要になります。
③債権者が上記期間内に異議を述べなかった場合は、承認したものとみなされます。
④仮に債権者から異議が述べられた場合、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
事業譲渡と会社分割の選び方
事業譲渡と会社分割は、事業や事業に関する権利義務関係を相手方に受け継がせる点で似ている部分はありますが、事業譲渡は取引行為、会社分割は組織再編行為という全く異なる行為の性質となります。
この行為の性質は、債権者保護手続きの要否の違い等、手続き的な部分で様々な違いをもたらします。事業譲渡か会社分割かどちらを選ぶかは、その目的により考えることが必要です。
以下では、特に重要な契約上の地位の移転の仕方や、債権者保護手続きの要否の違いについて説明をします。
事業譲渡と会社分割の違い
事業譲渡という行為は、会社の事業の全部又は一部を相手方に受け継がせる取引行為という性質を有しています。このような性質の場合、その事業に関する契約や権利義務関係は、個別に独立して受け継がれることになります。
譲渡者は、各契約関係の債権者から事業譲渡について個別に承諾を得なければなりません。一つ一つ個別に債権者から承諾を得る必要があるため、事業譲渡の場合は、会社法上、債権者保護手続きの規定は設けられておりません。
仮に、当該事業譲渡が、譲渡者の債権者を害するような行為であった場合、詐害行為として事業譲渡を取り消すよう請求することができます。
一方で、会社分割は、事業譲渡と異なり、会社法上の組織再編行為として位置付けられます。これは、分割する事業に関する契約や権利義務関係を包括的に受け継がせることになります。
つまり、事業譲渡のように、各債権者それぞれから承諾を得る必要はなく、まとめて権利義務関係を受け継がせることができます。ただし、債権者に個別に承諾を得る必要がない代わりに会社分割の場合は、債権者保護の観点から、会社法上、債権者保護手続きが定められています。
まとめ
ここまでご覧いただいた通り、M&Aの手法によっては債権者保護手続きが必要になることがあります。M&Aの手法を選択する時は、債権者保護に配慮しつつ、優先するM&Aの目的に応じて検討することがポイントになります。