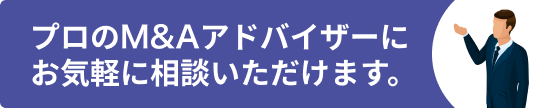企業買収時の会計処理|株式譲渡・事業譲渡時の仕訳について解説
公開日:2022年1月28日 最終更新日:2022年11月18日

企業買収の取引類型や採用する会計基準によって、会計処理が異なります。特に買収者にとって重要になるのは買収によって取得した「のれん」の処理です。本記事では、企業買収における会計処理について、主に買収者の視点に立って説明します。
目次
企業買収時の仕訳とは
「企業買収」とは、買収の対象となる会社の経営権を取得することです。企業買収は会社にとっても重要なイベントであり、その際にどのような会計上の影響が生じるか理解しておくことが重要になります。
ここでは、企業買収の代表的な手法である株式譲渡と事業譲渡について、会計上ではどのように仕訳する必要があるのかについて概要を説明します。
株式譲渡の場合の仕訳・会計処理
「株式譲渡」とは、買収者が金銭等の交付と引き換えに、対象会社の株式をその株主から譲り受けることです。たとえば、X社がY社を買収する際に、株主Zが保有するY社の株式を譲り受けることを指します。
後述する事業譲渡とは異なり、株式譲渡の取引の対象となる資産は株式のみのため、他の買収手法と比べて手続きが簡易的であることから、広く用いられる買収手法といえるでしょう。
ここでは、買収方法が株式譲渡による場合の仕訳・会計処理についての概要を説明します。
株式譲渡で買収した時点の仕訳3つのパターン
株式譲渡で買収した時点の仕訳では、取得した対象会社の株数の割合によって資産勘定が異なります。
ここでは、「子会社株式」「関連会社株式」「その他の株式」として処理する場合の3つのパターンについて説明しましょう。
1.子会社株式として仕訳する場合
たとえば、X社が現金1,000万円でY社からZ社株式の議決権の過半数を取得したとします。この取引は、X社の資産である現金が減少する一方で、「関係会社株式」という資産が増加します。したがって、この場合の仕訳は以下となります。
・(借方)関係会社株式:1,000万円
・(貸方)現金預金:1,000万円
X社はY社の議決権の過半数を取得しているため、「関係会社株式」の資産勘定として仕訳します。
2.関連会社株式として仕訳する場合
たとえば、X社が現金5,000万円でY社株式の議決権の1/3を取得したとします。この取引は、子会社株式の取得と同様に、現金が減少する一方で、同じ資産である株式が増加することになります。したがって、この場合の仕訳は以下となります。
・(借方)関係会社株式:5,000万円
・(貸方)現金預金:5,000万円
X社はY社の議決権の20%以上50%未満の範囲で取得しているため、「関係会社株式」の資産勘定として仕訳します。議決権の20%以上を取得していれば子会社であっても関連会社であっても関係会社株式として計上しますが、連結財務諸表作成のための連結修正における取扱いは異なりますので注意しましょう。
3.その他の株式として仕訳する場合
たとえば、X社が現金1,000万円でY社の株式の議決権を10%取得したとします。この場合も、上記と同様に、X社の資産である現金1,000万円が減少する一方で、資産である株式が増加することになります。したがって、この場合の仕訳は以下となります。
・(貸方)投資有価証券:1,000万円
・(借方)現金預金:1,000万円
20%未満の株式の取得であれば関連会社株式に該当しないため、この場合は「投資有価証券」として表示することになります。
株式譲渡で買収した後の仕訳
買収した時の仕訳だけではなく、買収した後も決算期において仕訳が必要になる場合があります。
これは、保有している株式が上場株式であり「投資有価証券」に該当する場合です。このケースでは、決算期において株式の評価替えの仕訳をする必要があります。
たとえば、X社が、現金1,000万円でY社の株式の議決権を10%取得したとします。その後、決算期では保有するY社株式の時価が1,300万円になっていましたが、保有するY社株式の議決権は10%から変動がありませんでした。
法人税率を40%とした場合、仕訳は以下のようにできます。
(借方)
投資有価証券:300万円
(貸方)
その他有価証券評価差額金:180万円
繰延税金負債:120万円
なお、保有する株式が非上場株式である場合や、上場株式であっても「子会社株式」「関連会社株式」に該当する場合は、決算期に仕訳する必要はありません。
株式譲渡の場合の仕訳の注意点
取得した会社が子会社になる場合で連結決算とする時は、のれんを認識して会計処理をする場合があります。
「のれん」とは、買収価格から対象会社の純資産額を引いた額のことをいいます。この差額を認識して、会計上の処理を行うことになります。
事業譲渡の場合の仕訳・会計処理
代表的な買収の方法として、前述の株式譲渡の他に「事業譲渡」があります。
株式譲渡では、対象会社の株式を譲り受けますが、事業譲渡の場合は、事業の全部又は一部を譲り受けます。譲り受けるものが事業である点で、株式譲渡とは大きな違いがあります。
事業譲渡の場合、事業に関する複数の資産を譲り受けることになります。事業譲渡における仕訳は、事業に関する複数の資産の仕訳が必要になる点で、株式譲渡の仕訳とは大きく異なります。
ここでは、事業譲渡によって買収した時点と、買収した後の仕訳について解説しましょう。
事業譲渡で買収した時点の仕訳
たとえば、X社が事業譲渡による方法でY社から資産を総額25,000万円で取得したとします。取得した資産と金額は、棚卸資産:2,000万円、土地:10,000万円、建物:5,000万円、機械装置:5,000万円、特許権:500万円とします。金額は全て時価です。
(借方)
・棚卸資産:2,000万円
・土地:10,000万円
・建物:5,000万円
・機械装置:5,000万円
・特許権:500万円
・のれん:2,500万円
(貸方)
・現金預金:25,000万円
この時、純資産額よりも高い価格で会社を買収した場合は、「のれん」が発生します。なお、事業譲渡における譲渡対象資産に課税資産が含まれる場合は消費税が発生しますので注意しましょう。
事業譲渡で買収した後の仕訳
事業譲渡で買収した後の仕訳では、決算期にのれん償却の仕訳が必要になります。のれんは20年以内の効果が及ぶと見込まれる期間にわたって経費として償却することができます。
たとえば、決算期におけるのれんの償却費が50万円であった場合の仕訳は以下となります。
・(借方)のれん償却費:50万円
・(貸方)のれん:50万円
出典:企業会計基準第 21号 企業結合に関する会計基準|企業会計基準委員会
事業譲渡の場合の仕訳の注意点
上記のとおり、対象会社の純資産よりも高い価格で買収するとのれんが発生し、仕訳の処理が必要になります。では、買収価格の方が低い価格で取得した場合はどうでしょうか。
この場合は「負ののれん発生益」というかたちで処理します。たとえば、資産価格3,000万円の事業を2,800万円で取得したとします。この場合の仕訳は以下のようになります。
(借方)
・事業資産:3,000万円
(貸方)
・現金預金:2,800万円
・負ののれん発生益:200万円
買収価格の方が低い場合、買収者は得をして取得したことになるので、負ののれんは利益として処理する必要があります。
のれんとは
「のれん」とは、前述のとおり買収金額から対象会社の純資産を引いた差額のことです。
たとえば、対象会社のブランド力、ノウハウ、人的資本等の無形固定資産がそれに該当します。無形固定資産は企業努力によって積み上げられるものですが、そこまでには長い時間を要します。
そのため、企業買収においてのれんを支払う意味は、自社で労力とお金を費やして無形固定資産の積み上げをするのではなく、それに要する時間を買う行為であると捉えることができるでしょう。
日本の会計基準と国際財務報告基準(IFRS)
日本の会計基準とは、「企業会計原則」をベースに企業会計基準委員会が設定した会計基準を合わせたものをいいます。対して国際財務報告基準IFRS(イファース/アイファース)は、世界共通の会計基準を目指して作成されたものをいいます。
日本の企業の多くは日本の会計基準を採用していますが、グローバルに事業を展開する企業においてはIFRSを採用する会社もあります。
日本の会計基準とIFRSの違いにおいて特に重要となるのは、のれんの処理です。日本の会計基準の場合、のれん償却は定められた期間で処理していくことが可能ですが、IFRSの基準ではのれんの償却は行われないため、日本の会計基準とは大きく異なります。
IFRSの基準に基づく場合、のれんの償却処理を行わない代わりに、のれんの価値が低下していないかを調べるために、毎期減損テストを実施することが要求されています。
譲渡企業側の仕訳
ここまで、買収者側の視点で企業買収時と買収後の仕訳について紹介してきました。
最後に、譲受企業側の視点からの株式譲渡時と事業譲渡時の仕訳について、例を挙げて説明するので、参考にしてください。
株式譲渡時の仕訳
たとえば、Y社がX社に対して、自社で保有する子会社Z社の株式を5,000万円(帳簿価格では4,000万円)で譲渡したとします。
この場合、Y社はZ株という資産が減少し、一方で現金が増加するかたちになります。しかし、Z社からすれば、株主がYからXに代わるだけのため、影響は受けません。したがって、仕訳は以下のようになります。
(借方)
現金預金:5,000万円
(貸方)
子会社株式:4,000万円
子会社株式売却益:1,000万円
事業譲渡時の仕訳
たとえば、Y社がX社に対して、自社が保有する事業Aに関する資産を譲渡したとします。
譲渡価格は時価で、A事業に関する棚卸資産300万円(簿価300万円)、土地10,000万円(簿価9,000万円)、建物5,000万円(簿価6,000万円)、特許権20,000万円(簿価10,000万円)の時価合計35,300万円とします。
この場合、Y社はA事業に関する資産が減少する一方で、現金が増加するかたちになるため、仕訳は以下のようになります。
(借方)
現金預金:35,300万円
(貸方)
棚卸資産:300万円
土地:9,000万円
建物:6,000万円
特許権:10,000万円
事業売却益:10,000万円
まとめ
本記事では、企業買収時の仕訳について、株式譲渡の場合と事業譲渡の場合それぞれについて説明しました。買収の方法が株式譲渡か事業譲渡によって、会計処理が異なることをご理解いただけたでしょうか。
買収者にとって特に重要になるのは、「のれん」の会計上の処理です。買収者にとってのれんを支払うということは、本来自社で行うべきである「無形固定資産の積み上げ」に要する時間と労力を買うことであり、企業買収の目的となるためとても重要といえます。
また、のれんの会計処理は採用する会計基準や買収の手法によっても異なってくるため、会計に関する高度な専門性が求められます。
実際の企業買収のケースにおいては、会計や税務の専門家に相談しながら進めることが多いため、企業買収の成功に向けた専門的なサポートを受けられるでしょう。
M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」では、プロのアドバイザーに直接相談することで、会社売却や資金調達に関する最新のトレンドや業界別のインサイトを知ることができます。まずはお気軽に無料でご相談ください。