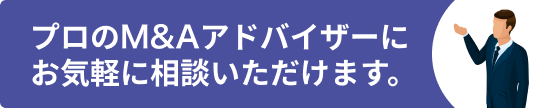株式譲渡の手続きを解説|株式譲渡に必要な書類一覧も紹介
公開日:2021年8月20日 最終更新日:2022年11月18日

本記事ではM&A(Mergers&Acquisitions・企業の合併と買収)のスキームの一つである「株式譲渡」の手続と必要書類について詳しく解説しています。株式譲渡を検討されている方は、ぜひご一読ください。
M&Aクラウドを利用すれば、買い手の責任者と平均1週間で面談することができます。経験豊富なプロのアドバイザーに無料相談することもできるので、まずは無料の会員登録をお試しください。
目次
株式譲渡とは
株式譲渡とは、株式の譲渡によって株主の地位を移転させることを言います。迅速かつ比較的簡便な手続により会社を売買できるため、中小企業のM&Aにおいてもよく使われているスキームです。
この記事では、株式譲渡をスムーズに行うための手続きや必要書類について説明します。
株式譲渡の手続書類
株式譲渡を実施する場合、会社法上の規定に従って手続きを進める必要があります。
ここでは、売手側の企業が「非公開会社」かつ「取締役会」非設置会社であり、譲渡承認を「株主総会」で行う場合の手続を解説していきます。
上記の場合、株式譲渡に必要な書類として、以下のものが挙げられます。
- 株式譲渡承認請求書
- 株主総会の招集に関する取締役の決定書
- 臨時株主総会招集通知
- 臨時株主総会議事録
- 株式譲渡承認通知
- 株式譲渡契約書
- 株式名義書換請求書
- 株主名簿
- 株主名簿記載事項証明書交付請求書
- 株主名簿記載事項証明書
売手側の企業は、株式譲渡を承認してもらうために譲渡承認請求を行い、これに対して取締役が臨時株主総会の開催を決定します。
その後、臨時株主総会を招集して承認の決議を行い、その議事録も作成します。承認された後は、株主名簿の記載事項を変更しなければなりません。
参考記事:
・株式譲渡で株式譲渡承認請求書が必要になる場合|記入方法や押印について解説
・株式譲渡の6つの手続き|必要な書類や注意事項4つも紹介
株式譲渡契約書
株式譲渡を行う場合、売り手企業が株式を譲り渡す代わりに、買い手はその対価を支払います。このとき、売り手と買い手の間で合意を得た株式譲渡の諸条件を記載するのが「株式譲渡契約書」です。
以下で、株式譲渡契約書において取り決めるべき具体的な項目を見ていきましょう。
株式譲渡契約書に記載する項目
株式譲渡契約書の中で取り決めるべき項目として、以下のものが挙げられます。
- 株式譲渡の合意
- 譲渡対価、支払方法、支払条件
- 株主名簿の書き換えへの協力義務
- 競業避止義務
- 契約解除
- 損害賠償
- 合意管轄
まずは、譲渡対象となる株式や譲渡対価などの主要な取引条件を取り決めます。さらに、株式譲渡後に一定期間、売り手が当該株式会社と競業する事業を営めない義務があること(競業避止義務)や、その他一般条項についての合意を記載します。
印紙貼付が必要なケース
株式譲渡契約書は、原則として課税文書に該当しないため、契約書に収入印紙を貼付する(印紙税を納付する)必要はありません。
ただし、株式譲渡契約書の中で譲渡対価を受領した旨を記載する場合は、「領収書」としての性質を帯びるため、契約金額に応じた収入印紙を貼付する必要が生じることには注意が必要です。
株式譲渡手続準備の注意点
売り手が親族経営企業であるような場合には、前述のような煩雑な手続きを省略したいと考えるケースも多く見られます。
しかし、株主総会手続きに不備がある場合や、株式譲渡手続きが適切に行われていない場合、裁判によって決議そのものが取り消されてしまうリスクがあります。
法務局や官庁からのチェックが入らないとはいえ、将来トラブルにならないようにするためにも、会社法に従って厳格に手続を行う必要があります。
ここからは、株式譲渡手続準備の際の具体的な留意点について見ていきましょう。
参考記事:
・株式売却(株式譲渡)を考えるなら検討すべき4つの問題とは|税金についても解説
株券発行会社か
株式会社の中には、自社で「株券」を発行している会社もありますが、自社が株券発行会社であるかどうかは、会社の定款か登記簿謄本で確認できます。
株式譲渡の際、自社が株券発行会社である場合は、買い手側に実際に株券を交付する必要があるため、注意が必要です。
一方、株券不発行会社であれば、このような手続をする必要はなく、株式譲渡は当事者間の合意(意思表示)のみで成立します。
譲渡制限付き株式か
自社が譲渡制限付き株式であるかどうかは、会社の定款か登記簿謄本で確認できます。譲渡制限つき株式であれば、上述のとおり承認手続が必要となるため、事前に確認しましょう。
譲渡制限とは、会社が自社の株式を譲渡する際に、会社の承認を要するということです。そのような取り決めを持った株式を「譲渡制限付株式」といい、非公開企業である多くの中小企業がそのような形態をとっています。
株式譲渡と課税
株式譲渡によって譲渡対価を得る場合には、譲渡所得税等の課税対象となります。
このとき、売り手が個人、非公開会社、上場会社であるかによって課税の種類や金額の算定方法が異なります。税務上の問題が生じないよう、税理士に相談しましょう。
無償で株式譲渡する場合
株式譲渡の対価をとらない、すなわち無償譲渡した場合は「贈与」として扱われるため、「贈与税」が課税されます。
税務上の問題が生じないよう、税理士に相談しながら進めましょう。
株式譲渡の手続
ここからは、実際の株式譲渡の手続について解説します。
いざ株式譲渡を行おうとする場合に困らないよう、必要な手続を事前に把握し、適切かつ円滑に進められるように準備しておきましょう。
株式譲渡承認請求
非公開会社の譲渡制限つき株式を譲渡する株主は、会社に対して譲渡承認請求を行う必要があります。
特に決まった書式はありませんが、譲渡する株式の種類・数、譲渡する相手方の住所・氏名、株主(売り手)の情報等を記載のうえ、会社に提出します。
なお、買い手である株式取得者も、株主名簿の名義人である売り手の株主と一緒に、会社に対して承認の可否を決定するよう請求することができます。
取締役会または株主総会の招集と決議
株式譲渡承認請求を受けた場合、取締役会を設置している会社においては取締役会を、それ以外であれば株主総会を開催します。
開催にあたっては、それぞれ招集手続を行う必要があります。株主総会を開催する場合は、まず取締役が株主総会の招集について決定します。そして、取締役会または株主総会において当該株式譲渡の承認可否を決議します。
株式譲渡契約締結
上記を経て、株式譲渡契約が承認されたら「株式譲渡契約書」を作成します。
株式譲渡契約書の原本2通を作成・製本し、売り手と買い手の双方が記名・押印します。収入印紙を貼付する場合は消印も忘れないようにしましょう。
契約書に必要事項を記入し、押印が済んだら、株式譲渡契約が締結されたことになります。
株式譲渡の対価支払
株式譲渡契約締結後は、買い手には売り手に対価を支払う義務が生じます。
株式譲渡契約書の条件どおりに譲渡対価が支払われているか確認し、もし支払いがなされていない場合には、直ちに買い手へ確認しましょう。
株主名簿の名義書き換え
株式譲渡契約を締結した後は、譲渡した株式の名義を売り手から買い手に変更するために、会社に対して名義書換の請求を行います。
株券不発行会社の場合であれば、売り手と買い手が共同して名義書換を請求し、株券発行会社であれば、株券を提示することによって買い手単独で請求することが可能です。
なお、売り手企業において株主名簿管理人が選任されている場合は、当該管理人が手続を行います。
有限会社の譲渡について
平成18年の会社法施行にともない、新たに有限会社は設立できなくなり、施行時に存在していた有限会社は、登記申請等の特段の手続きを経ずに会社法上の株式会社として存続することになりました(整備法上の特例有限会社)。ただし、商号に引き続き有限会社の文字を使用しています。
したがって、有限会社における株式譲渡手続は、基本的に株式会社の場合と同様です。
ただし、有限会社の株式には全て譲渡制限がついているため、譲渡承認手続が必要となる点を押さえておきましょう。
まとめ
本記事では、株式譲渡を行う際の手続と必要書類について解説しました。株式譲渡を行う場合、会社法の規定に従って適切に所定の手続を行う必要があります。
手続に不備がないかどうか、そのつど、弁護士や司法書士、税理士といった専門家に相談しながら着実に進めていくようにしましょう。
M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」では買収をしたい企業が、欲しい企業の要件を記事として公開中です。 買い手企業を手軽に探すことができるほか、M&Aアドバイザーに無料相談することも可能。お気軽にご相談ください。