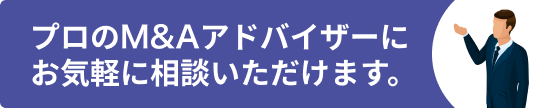スタートアップが押さえるべき事業計画書のポイントを紹介!必要な8つの要素とは
公開日:2021年10月8日 最終更新日:2022年11月18日

本記事では、スタートアップ企業が資金調達を実施するうえで、欠かすことのできない事業計画書の作成方法について解説しています。
どこから資金調達をするのかで事業計画書の要素は大きく変わります。目的別に合わせた事業計画書の書き方やポイントを押さえるようにしましょう。
目次
スタートアップの事業計画書が必要なシーン
スタートアップにとって、事業計画書が必要になるのは資金調達のタイミングです。
例えば、売上が大きくなるにつれて運転資金が必要になったときや、新しく設備投資をしたいと考えているが、それに伴う原資が足りないという場合には資金調達が必要になります。
本記事では、スタートアップに欠かすことのできない資金調達の際に必要となる事業計画書のポイントについてわかりやすく紹介していきます。
スタートアップとは
スタートアップという略称はシリコンバレーが起源で、いわゆる「GAFA」と呼ばれるGoogle、Apple、Facebook、Amazonといった短期間で大成長した企業がスタートアップが指す企業として挙げられています。
いつ会社が設立されたのかという情報よりも、抱えている企業の問題解決の規模が大きく、大きなイノベーションを起こす可能性が高い企業がスタートアップと呼ばれています。
事業計画書とは
事業計画書とは、金融機関やVCからの資金調達の際に必要な資料のことをいいます。
事業計画書には、今後どのように事業を運営していくのかを記載し、定量面として具体的な売上目標・数値目標も折り込むようにします。
そのため、事業計画書を見れば、投資家たちは自分たちの出資・貸し出した資金がどのように使われるのかを一目で理解できます。
スタートアップの事業計画書の作成方法
スタートアップの事業計画書の作成方法にはポイントがあります。
事業計画書を見て融資や投資の実行を判断するのは、銀行員や投資家などの専門家であることを大前提として考えます。そのため、見やすく数値の蓋然性が高い資料を作成するのはもちろんのこと、そのほかにも注意点がいくつかあります。
ここからは、事業計画書を作成するための3つのポイント、および8つの要素について、わかりやすく解説していきます。
スタートアップの事業計画書の3つの特徴
事業計画書には2パターンの書き方があります。
1つ目は、既存会社が資金調達する際に必要な事業計画書です。そして、2つ目は創立間もないスタートアップの事業計画書です。2パターンの事業計画書の違いについては以下で詳述します。
まずはスタートアップの事業計画書を作成する際の3つの特徴についてみていきましょう。
特徴1:成長性や将来性を重視する
まずは、成長性や将来性に重点を置くことが大切です。既存会社の数値には、今までの実績をもとにした数値が織り込まれますが、スタートアップの場合にはビジネスの将来性が必要になります。
足元での収益化ができていない事業がほとんどであるため、スタートアップの場合は将来性を重視した事業計画書の策定が必要になってきます。
特徴2:独自性を重視する
次に、独自性を重視した事業計画書を作成することが大切です。特に、革新的なイノベーションを起こそうとしている場合には、その事業からどれだけの収益が生まれるのか不明確な場合があります。
こうした際の資金調達の場合には、その事業の社会的インパクト、サービスの独自性、競争優位性などが重視されます。そのため、事業計画書にも、独自性を重視した内容を盛り込みましょう。
特徴3:市場ニーズを重視する
最後に、市場のニーズを重視した事業計画書を策定することが大切です。どれだけ新しい商品を開発・ローンチしようとしたところで、そこに市場のニーズがなければ売上にはつながりません。
特に、アイデアベースのプロダクトアウトの場合は、市場ニーズの観点を欠いた事業計画書が策定されるケースがあります。このため、事業計画書には市場のニーズを必ず組み込むようにしましょう。
スタートアップの事業計画書8つの要素
次に、スタートアップの事業計画書を作成する際の8つの要素を見て行きましょう。特に、スタートアップが事業計画書を作成する際に欠けてしまうことが多いポイントについて解説しています。それぞれ参考にしてみてください。
要素1:経営者の紹介
まず、事業計画書には経営者の紹介を欠かさないようにしましょう。スタートアップの事業計画書は特性上、数値の正確性に欠けることがあります。
このことから、既存会社の事業計画書よりも、経営者などの「人」にあたる部分の重要性が高くなる傾向があります。
経営者の経歴や今後どういった企業を経営していきたいのか、という理念などは欠かすことなく盛り込むようにしましょう。
要素2:ターゲットユーザー
次に、ターゲットユーザーを明確にした事業計画書を策定することが重要です。特に、プロダクトアウトの商品は明確なターゲットユーザーが決まっておらず、結局その商品は誰が買うのかが明確になっていないケースがあります。
ターゲットユーザーが決まっていないサービス・商品は、誰にも見向きもされないモノになることが多いため、必ずターゲットユーザーを確定させておきましょう。
要素3:解決すべき課題と解決策
事業計画に盛り込む内容として、解決すべき課題と解決策があります。まず、事業を通してどういった課題を解決したいのかを明確にしなければ、そのサービス・商品が何の役に立つのかがわかりません。
また、問題をどのように解決するのかまで明確になっていないと、商品が顧客に対して刺さるモノなのかを判断することができないのでご注意ください。
要素4:市場規模と成長性
市場規模と成長性についても記述が必要です。どれほど商品・サービスが優れていようとも、市場規模が小さく、今後の発展の見込みが低いということであれば企業の持続的な成長は難しくなります。
どれほどシェアを獲得しても、元々の市場規模が小さい場合は、投資家や銀行から資金調達をすることは難しいと考えて良いでしょう。
要素5:競争戦略と差別化ポイント
競争戦略と差別化ポイントについても記載するようにしましょう。スタートアップに求められるのは、今までにない革新的な社会問題の解決方法と言っても過言ではありません。
このため、他社と比較したときに自社がどれほど独自性が高いのか、さらには差別化のポイントはどこにあるのかを具体的、かつ客観的に記載することが大切になります。
要素6:ビジネスモデル
ビジネスモデルについても記載が必要です。このときに、特に大切なのは初めて見た人が一目でわかるように、図式化されているかです。
ビジネスモデルについては、収益、サービス、データの流れ、コスト構造までわかりやすく説明できていると、事業計画書を見る人にわかりやすい資料が出来上がります。
なお、コスト構造については、会社の損益計算書の流れと同様に、売上、売上原価、売上総利益などにまで言及できると数字の客観性が高まります。
要素7:戦略実行における数値計画
戦略の実行における数値計画を作成することも大切です。特に、数値計画はKPI(Key Performance Indicator)をもとに算出すると良いでしょう。
KPIは、KGI(Key Goal Indicator)から逆算された数値を達成するための最重要事項です。一般企業の場合、KGIは売上になることが多いため、KPIも同様に数値で示される場合が多くなります。
数値を使っての目標は計画を達成できたのか否かが定量的に可視化できるため、客観性も高まります。特に創業間もないスタートアップは、必ず数値計画を盛り込むようにしましょう。
要素8:資本政策等
事業計画書には、資本政策等も盛り込んでおくことでより丁寧な資料になります。
たとえば、今後資本金はいくらまで増資する予定なのか、現在の株価はおおよそどのくらいで、今後KPIを達成した際には株価は何倍になるのかまで記述しましょう。
イグジットとして上場などを見込んでいる場合には、類似企業の株価は上場で何倍になったのかをリサーチしたうえで記載しておくと、投資家にとっても出口戦略の見えやすい資料が出来上がります。
【目的別】事業計画書のポイント
事業計画書を策定する際に大切なポイントは、事業計画書を提出する相手に合わせて説明の密度を変えることです。
たとえば、資金調達を検討する際にも資金調達先が金融機関なのか、VC(ベンチャーキャピタル)などの投資家なのかによって事業計画の説明の仕方は大きく異なります。
そのため、事業計画書はテンプレートを1部作成し、その後は説明の相手によって使い分けることをおすすめします。ここでは、目的別の事業計画書のポイントをわかりやすく3つの視点から説明します。
ポイント1:金融機関からの融資
金融機関からの融資を検討する場合には、返済の蓋然性が高い計画書を策定する必要があります。
この際、事業計画に盛り込むのは事業の内容のみならず、事業によって生まれる収益・コスト、そして手元に残る資金繰表まで作成しておくと良いでしょう。
金融機関からは計算のエビデンス確認のため、エクセル資料での提出を求められることもあるため、なぜその数値になるのかを明確にしておくことが必要です。
ここで誤った数値を提示してしまうと、融資の審査でマイナスに働く恐れがあるため、気をつけるようにしましょう。
ポイント2:投資家からの投資
投資家からの投資を受ける場合には、個人投資家の好みを把握しておく必要があります。
たとえば、投資家のなかにはイグジットを重要視している人もいれば、事業の実現性や経営者の夢に賭ける人もいます。そのため、投資家に合わせた事業計画書を作成しておくことが重要になります。
また、長いプレゼンテーションを嫌う人もいるため、ピッチ形式で説明ができるように準備する必要もあります。
ポイント3:ベンチャーキャピタルからの投資
VCは、イグジットに伴う株式の売却益を重要視しているケースが多くみられます。このため、自社の事業がどれだけ可能性があり、成功によってどれだけのリターンが見込まれるかを中心に事業計画書に記載する必要があります。
また、投資ファンドによって重視するものは異なっているため、各VCに合わせた資料を作成することが推奨されます。
ポイント4:公的機関からの補助金や助成金
公的機関からの補助金や助成金を交付してもらう場合には、基本的には返済義務はありません。
そのため、何かをアピールするというよりは、応募事項にあった内容をしっかりと盛り込むことが必要になります。必ず手続き内容を確認し、そもそもの条件が自社に合っているのかを注意したうえで応募をするようにしましょう。
まとめ
本記事では、スタートアップにおける事業計画書の策定方法を詳しく紹介しました。事業計画書は1つを作ってから使い回すのではなく、目的によって使い分ける必要があることがお分かりいただけたと思います。
資金調達には今回紹介した方法のほかに、業務提携などのM&A手法を利用したスキームもあります。出口戦略としてのM&Aも、スタートアップにとっては重要な方法になります。
M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」では、会社を買いたい企業が、欲しい企業の要件を記事として公開中です。買い手となる企業を手軽に探すことができるほか、M&Aアドバイザーに会社売却について無料相談することも可能です。お気軽にご相談ください。