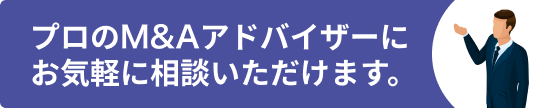事業譲渡における仕訳方法とは?4つの税務処理・注意点についても解説
公開日:2021年7月29日 最終更新日:2022年11月17日

事業譲渡の際は、譲渡側・譲受側ともに適切に税務処理する必要があります。税務処理の方法を誤ると、修正申告や更正の請求を行わなければならないことがあるほか、追徴課税を受ける恐れがあります。この記事では、事業譲渡における仕訳方法について詳しくご紹介します。
目次
事業譲渡とは?
事業譲渡はM&Aの形態の1つです。事業を譲渡する側と譲受する側で、必要な税務処理が異なります。
今回は、事業譲渡における税務上の取扱いから注意点まで詳しくご紹介します。なお、この記事で紹介する仕訳は税務上の取扱いを示したものであり、財務会計上の仕訳とは異なる場合がある点についてあらかじめご了承ください。
事業譲渡の定義
事業譲渡はM&Aのスキームのひとつで、判例によれば、「一定の事業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部又は重要な一部を譲渡し、譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動の全部又は重要な一部を譲受人に受け継がせ、それによって譲渡会社が法律上当然に、改正前商法25条(会社法21条に相当)に定める競業避止義務を負う結果を伴うもの」を言います。
つまり、事業譲渡は会社が営む事業の一部または全てを他社に譲渡することを言います。事業譲渡は、複数の事業を行なっている企業において「選択と集中」を行うため、中小企業において事業承継を行うためなど幅広い目的で利用されることがあります。
参考記事:事業譲渡のメリットとデメリット15選|契約完了までの流れも徹底解説!|M&A to Z
事業譲渡の税務処理
事業譲渡の際には、適切な仕訳による税務処理が必要です。事業譲渡の会計処理について、のれんの取扱いにも触れながら詳しく解説します。
のれんとは
事業譲渡では、譲受側が事業を受け取った対価を譲渡側に支払います。対価は、事業の純資産額(資産-負債で算出)よりも多額になることが一般的です。この対価と純資産額の差額が「のれん」です。
例えば、純資産30億円の事業を40億円で譲受した場合、差額の10億円が「のれん」となります。
純資産額を超える対価を支払う理由は、譲渡側が持つブランドや技術、ノウハウ、成長性など目に見えない価値(純資産額に含まれない価値)を評価するためです。
参考記事:のれんとは?M&A成功のために知っておきたい「のれん」の評価の高めかた、減損の防ぎかた|M&A to Z
一方で、「負ののれん」というものも存在します。
負ののれんとは、譲渡側の純資産額よりも少ない対価を支払った場合の差額のことを指します。例えば、総資産40億円、負債30億円で純資産が10億円の事業を5億円で譲受した場合は、5億円が負ののれんとなります。
負ののれんが生じるケースは、業績が悪化していたり多額の損害賠償を抱えていたりする場合などです。負ののれんが生じるようなM&Aはあまり多くなく、実務上はのれんが発生するケースがほとんどです。
参考記事:負ののれんが発生するM&Aとは?|負ののれんの原因、売り手企業と買い手企業に与える影響|M&A to Z
なお、「のれん」「負ののれん」は財務会計上の用語であり、税務上は「のれん」「負ののれん」に類似する概念として「資産調整勘定」「差額負債調整勘定」というものが存在します。
ここからは税務上の取扱いに関しても「のれん」という用語を使用しますが、「資産調整勘定」をわかりやすく言い換えたものと理解してください。
事業譲渡の基本的な税務処理
譲受側は、対象となる資産及び負債を時価で取得します。そのため、会計処理の際も時価で計上する必要があります。譲受する資産を借方に、対価として支払う現金預金(売却価格)を貸方に計上してください。
例えば、X社から以下のような事業xを譲り受けた際の譲受人Y社の会計処理は下表1のようになります。
設例1
①X事業の概要(単位:千円)
資産の帳簿価額:10,000
資産の時価:12,000
負債の帳簿価額:8,000(時価同じ)
②譲渡対価(現金預金):4,000
表1:譲受人Y社の税務処理
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額(千円) | 勘定科目 | 金額(千円) |
| 諸資産 | 12,000 | 諸負債 | 8,000 |
| 現金預金 | 4,000 | ||
のれん(資産調整勘定)が発生する場合の税務処理
譲受人が受け入れる純資産額(資産・負債の差額)と譲渡対価との差額は「のれん(資産調整勘定)」として計上します。
先ほどの設例の一部を変更し、Y社がX社のx事業を現金預金6,000千円で譲り受けた場合、以下のように処理します。
設例2
①X事業の概要(単位:千円)
資産の帳簿価額:10,000
資産の時価:12,000
負債の帳簿価額:8,000(時価同じ)
②譲渡対価(現金預金):6,000
表2:譲受人Y社の税務処理
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額(千円) | 勘定科目 | 金額(千円) |
| 諸資産 | 12,000 | 諸負債 | 8,000 |
| 資産調整勘定 | 2,000 | 現金預金 | 6,000 |
「資産調整勘定」は税務上5年で償却します。なお、会計上ののれんは20年以内の期間にわたって毎期定額を償却します。
負ののれん(差額負債調整勘定)が発生する場合の仕訳方法
負ののれん(差額負債調整勘定)は貸方に計上します。
設例1の一部を変更し、Y社がX社のx事業を現金預金1,500千円で譲り受けた場合、以下のように処理します。
設例3
①X事業の概要(単位:千円)
資産の帳簿価額:10,000
資産の時価:12,000
負債の帳簿価額:8,000(時価同じ)
②譲渡対価(現金預金):1,500
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額(千円) | 勘定科目 | 金額(千円) |
| 諸資産 | 12,000 | 諸負債 | 8,000 |
| 現金預金 | 1,500 | ||
| 差額負債調整勘定 | 2,500 | ||
差額負債調整勘定は、資産調整勘定と同様に税務上5年で償却します。なお、会計上負ののれんは「負ののれん発生益」として対象となる会計期間の特別利益に計上されます。
事業譲渡で気をつけたい税務上の留意点
事業譲渡の際は、譲渡側・譲受側ともに税務上の論点が生じます。事業譲渡において注意すべき税務処理について詳しくご紹介します。
1:法人税
譲渡側は、資産・負債を譲渡したことになるため、貸方に譲渡益を計上します。獲得した譲渡対価が譲渡した資産・負債の帳簿価額を上回る場合は、利益を得たことになります。
事業譲渡で得た利益は企業の益金となり、課税所得が発生した場合には法人税をはじめとして、事業税や住民税などの納税が必要です。法人税や地方法人税、法人住民税、事業税所得割を合わせた実効税率は30.62%です。
2:のれん
すでに説明した通り、事業譲渡の場合、税務上ののれんが発生する場合があります。
具体的には、税務上ののれんが発生した場合は、のれんは「資産調整勘定」、負ののれんは「差額負債調整勘定」として処理します。
3:消費税
事業譲渡によって得た課税資産に対して消費税が発生します。課税資産には主に次のような資産が該当します。
- 有形固定資産(建物や機械設備など形を持つ資産)
- 無形固定資産(技術やノウハウ、営業権、商標権、特許権など形を持たない資産)
- 棚卸資産(販売するために企業が保有する商品や製品)
買い手は事業譲渡の対価とあわせて消費税を支払います。なお、有価証券や売掛金などは消費税の課税対象ではありません。
4:非課税売上
3.で説明した通り、事業譲渡において課税資産を譲渡した場合には消費税を受け取ることとなりますが、土地や有価証券などの譲渡(非課税売上)についても注意が必要です。特に、事業譲渡では土地を譲渡するケースがあるため、チェックしておきましょう。
この非課税売上に関してポイントとなるのが、課税売上割合です。課税売上割合とは、簡単に言えば会社の売上に占める課税売上高の割合のことです。会社が納付すべき消費税を計算するにあたり、仕入税額控除という概念が存在します。控除される仕入税額の計算においては通常、課税売上割合をもとに按分計算を行います。
したがって、事業譲渡により非課税売上が膨らみ、課税売上割合が減少することで控除仕入税額の計算に影響を及ぼすことがあるため、事業譲渡を行う際の消費税の取扱いについては税理士などに早めに相談することをおすすめします。
事業譲渡の2つのメリット
M&Aを検討する際は、手法ごとのメリットとデメリットを確認しておくことが大切です。ここでは、事業譲渡のメリットを2つご紹介します。
1:事業の一部を売却することができる
株式譲渡が対象会社を丸ごと売却するのに対し、事業譲渡では事業の一部のみを売却できます。例えば、継続したい黒字事業は残し、採算が取れない赤字事業だけを売却できるのです。
そのうえで、事業譲渡によって獲得した資金を残った事業に投資することもできます。その他、譲渡代金を元手に債務を減らして財務状況を改善したり、譲渡代金を元手に新事業を立ち上げたりも可能です。
2:譲渡益が法人の利益となる
事業譲渡を行う主体は会社であるため、譲渡益は会社の利益を構成します。
赤字事業を譲渡した場合は、条と事業に係る人件費や設備投資などを削減できるため、キャッシュ・フローが改善することも期待できます。
M&Aクラウドを利用すれば、買い手の責任者と平均1週間で面談することができます。経験豊富なプロのアドバイザーに無料相談することもできるので、まずは無料の会員登録をお試しください。
事業譲渡の注意点3つ
1:株式譲渡と事業譲渡では課税対象となる主体が異なる
株式譲渡の場合、株主が獲得した譲渡益に対して課税されます。株主が個人であれば所得税が発生し、法人であれば法人税が生じます。一方、事業譲渡では事業を譲渡する主体は会社であるため、株主ではなく会社に対して課税関係が発生します。
参考記事:株式譲渡と事業譲渡の違いを比較!選択すべき基準も解説|M&A to Z
2:事業譲渡では個人株主の手取り額が減少する場合がある
個人株主の場合、株式譲渡であれば株主は約20%の所得税を負担することとなります。
一方で、事業譲渡で事業を清算する際には、事業譲渡によって会社が獲得したキャッシュを個人株主に還元するために、まずは売却益に対する法人税を負担したうえで、残余部分に対して配当や退職金等を用いてキャッシュを吸い上げる必要があります。
いずれの場合も法人税と所得税が課税されるため、株式譲渡と比較して個人株主の手取り金額が減少することがある点に注意しましょう。
3:資産の種類によって消費税がかかる
事業譲渡で売却される資産のうち、消費税が課税される代表的な資産として以下の3つがあげられます。
- 有形固定資産(土地を除く)
- 無形固定資産
- 棚卸資産
有形固定資産は前述したとおり、建物や設備、車両、船舶といった目に見えて形がある資産です。なお、土地の有形固定資産ですが、消費税の課税対象ではありません。
無形固定資産は、特許権や意匠権といった知的財産、漁業権のような営業権など、目に見えない形がない資産のことです。
棚卸資産とは、販売や加工を目的に所有する資産のことで、商品や原材料などが該当します。「在庫」と言うとわかりやすいのではないでしょうか。
事業譲渡における税務処理とメリットや注意点を理解しよう
事業譲渡では、のれん(資産調整勘定)や法人税・消費税など、会計・税務に関していくつか確認しておきたいポイントがあります。
会計・税務におけるミスは会社の損失に繋がるため、会計・税務上の取扱いや注意点を理解しておくことが大切です。
M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」では、プロのアドバイザーに直接相談することで、会社売却や事業譲渡に関する最新のトレンドや業界別のインサイトを知ることができます。まずはお気軽に無料でご相談ください。