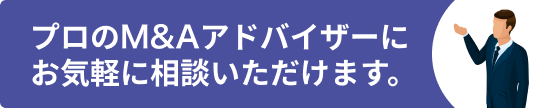会社の承継を成功させる会社分割|吸収分割のメリットを解説
公開日:2021年8月20日 最終更新日:2022年11月18日

本記事ではM&Aの手法の一つ、会社分割についてわかりやすく説明しています。会社分割には吸収分割と新設分割がありますが、その種類とメリットや注意点をまとめています。M&Aを検討されている経営者の方はぜひご覧になってください。
目次
会社分割とその種類とは?
会社分割とは、企業の組織再編の手法の一つで、会社を他の会社、あるいは新設する会社に分割することをいいます。
会社分割には吸収分割と新設分割がありますが、どちらもややこしくわかりづらいと思ってしまうかもしれません。
本記事を読むことで、会社分割について理解ができ、吸収分割と新設分割それぞれの違いについて、メリットとデメリットを説明します。
現在会社分割を検討されている方、今後M&Aをする際のスキームの選択肢として会社分割を検討されている経営者の方は必見です。
吸収分割とは
吸収分割とは、既存事業を他の会社に引き継ぐ(分割する)ことをいいます。
他の会社に事業を分割することで、事業を分割する会社(分割会社)は対価を受け取ることができます。対価として受け取るのは金銭、株式です。
次に紹介する新設分割との違いは、分割する事業が既にある会社に吸収されるのか、新設された会社に分割されるのかの違いです。
新設分割とは
新設分割とは、既存事業を新設した会社に分割することを指します。
先ほどの吸収分割は、既に存在する会社に特定の事業を分割するのに対し、新設分割では新しくできた会社に事業を分割するのが違いになります。
新設分割を利用するメリットは、分割事業に関する権利関係を包括的に新設会社に引き継ぐことができることです。
確認作業の工程が吸収分割と比して減るため、各権利関係を全て個別で確認が必要な事業譲渡と比較すると、スピーディーな手続きができることがメリットです。
会社分割の対価の受け取り方法
分割会社は事業を譲り渡すことでその対価を受け取ることができます。
この対価は、株式、金銭の2種類がありますが、従前は誰が受け取るかによって2つの方式に分かれていました。事業の分割の対価を分割会社が受け取ることを「物的分割(分社型分割)」、事業の分割の対価を分割会社の株主が受け取ることを「人的分割(分割型分割)」と呼びますが、「人的分割」は会社法改正(2006年)で廃止されています。
そのため、現在は「物的分割」のみが吸収分割のみが残っています。
しかし、実際のところは「物的分割」を実施し、株式や金銭を受領した後に、株主に利益剰余金を配当することで、ほぼ「人的分割」同様の効果を得ることも可能です。
参考記事:
・事業の選択と集中に使える“会社分割”とは何か?メリット・デメリット、手続きを解説
・事業譲渡と会社分割の違い|事業譲渡と会社分割のメリット・デメリット
吸収分割はどう活用すればいい?
吸収分割を活用するにはどうすればいいのでしょうか。
新設分割が新しく会社を新設するため、会社設立の手続きを踏まなければならないのに対し、吸収分割では既に存在する会社に事業を譲渡するため、会社設立の手続きを省略することで手続きがより簡易だというメリットがあります。
このため、新たな許認可の取得や会社規定を整備しなければならない新設分割と比べて、よりスピーディーな事業移転を検討している売り手にとってみれば手離れが早いことがメリットといえます。
例えば、不採算事業の売却の選択肢として吸収分割を検討されている場合は、吸収分割は適しているといえます。このように、自社の状態に合わせて適切なスキームを利用することをおすすめします。
吸収分割と事業譲渡はどう違うの?
吸収分割と混同しがちなスキームの一つに事業譲渡があります。
吸収分割と事業譲渡の違いは主に3点です。
(1)権利義務の承継における個別確認の違いです。吸収分割が事業承継に関して、債権者、労働者などからの同意なしに承継を進めることができるのに対して、事業譲渡では各々に個別契約を巻かなければなりません。
(2)債権者保護手続きについての違いです。対象の事業承継の分割に際し、各債権者からの異議申述期間を準備しなければならないのが吸収分割のデメリットといえます。この他にも、債権者保護手続きの書類の準備が必要になるので手間がかかる可能性があります。
(3)労働契約承継法が適用されるか否かです。労働契約承継法とは、簡単にいえば、会社分割で移籍することになる従業員も、そうでない従業員も会社分割前と同様の条件で雇用契約が保たれるための法律です。
吸収分割の5つのメリット
ここからは吸収分割のメリットとについて5つご紹介していきます。基本的にベースになるものは、吸収分割は手続きが他のM&Aと比べても軽く、扱いやすいということが挙げられます。
整理したい事業だけを切り出せる
1つ目の吸収分割のメリットは、整理したい事業のみを切り出せることです。
例えば、現在事業のセグメントの中で不採算事業がある場合には、その部分のみを吸収分割の対象事業として選択することができます。
特に、経営戦略として選択と集中を掲げている企業にとっては、ノンコア事業による収益の劣化は避けなければなりません。こうしたノンコア事業の売却にも使える手法として吸収分割は利用できます。
会社新設に比べて必要な手続きが少ない
新設分割と比較すると、吸収分割の方が必要な手続きが少ないのが2つ目のメリットといえます。新設分割の場合には、会社を新しく設立するという手間が発生してしまいますが、会社分割の場合には既にある会社への事業の譲渡になるため、会社の設立の手間がありません。
また、他の事業譲渡などと比較したい際に、会社分割は包括承継であるため、事業の許認可などの再取得や、従業員との個別労働契約締結などが不要です。
もちろん、例外はあるので一概に上記の個別契約が全て不要とは言い切ることはできませんが、それでも大体のケースにおいては他のM&Aよりも手続きが少なく、シンプルだといえます。
少ないキャッシュでも実行できる
少ないキャッシュでも実行できるのが吸収分割を利用する3つ目のメリットです。
M&Aを利用した買い手は、基本的には譲渡対価の支払いに多額の現預金を利用するため、その後のキャッシュフローが痛む可能性があります。つまり、買い手にとってM&Aのネックになるのは、どのように譲渡対価を準備するかという問題です。
吸収分割であれば、事業を受け取る対価として株式を交付するスキームも使えます。
株式交付であれば、既存株主からの理解さえ得られれば、キャッシュフローが痛むことなく事業を吸収できますので、買い手としてはハードルが低くなります。
このため、売り手としては他のM&Aスキームを利用するよりも事業を売却できる可能性は高くなります。
従業員も承継会社に引き継がれる
4つ目のメリットは従業員も承継会社に引き継げることです。
2つ目のメリットでも触れていますが、従業員は基本的に包括承継で今までと同条件で承継会社に引き継ぐことができます。
労働契約承継法に基づいて、従業員の同条件での雇用の契約が見込まれるため、経営者からすると雇用が継続される点でメリットといえるでしょう。
出典:会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)の概要|厚生労働省
今後のシナジー効果が見込まれる
5つ目のメリットは、今後シナジー効果を促しやすいスキームの選択が可能であることです。
買い手は吸収分割の対価を株式で支払うことができます。
株式が入った後は、互いに関係会社となるため、その後の事業での協力体制が築かれることが期待されます。関係会社になることで、互いのリソース、仕入れ、販売先を相互に利用した新しいシナジーが生まれる可能性があることも吸収分割のメリットです。
吸収分割の注意点
吸収分割には今まで説明してきたようにメリットも多くありますが、注意しなければならないポイントもあります。
ここからは、吸収分割をする際に注意すべきポイントを紹介します。
株価の変動
特に上場企業の場合に注意すべきなのは株価の変動です。事業を切り離すことにより、企業価値は下がるケースが多いため、株価が落ち込むことが懸念されます。
一方で、不採算事業の切り離しや、ノンコア事業切り離しによる経営リソースの選択と集中などポジティブな吸収分割の場合には、逆に株価が上がる可能性もあります。
どちらにせよ、事業を切り離すため、株価への影響は少なからずあると考えておく方が良いでしょう。
従業員の退職や企業文化の変化による混乱
従業員の退職や企業文化の変化による混乱が起こる可能性があることにも注意が必要です。
吸収分割により売却された事業に従事する従業員は、待遇は今までと同じといえども少なからず環境の変化の影響を受けます。
例えば、企業文化が変化することにより、退職を考える従業員も出てくる可能性もあります。
こうした事態を避けるためにも、事前に従業員とは十分なコミュニケーションをとっておく必要があります。
吸収分割の法務上の注意点
吸収分割を行う際には気をつけなければならないポイントがいくつかあります。
まずは株主総会についてです。基本的には株主総会を開催する必要があります。
簡易分割(詳しくは後述します)を利用した際は、株主総会の承認を省略できます。
しかし、例え簡易分割の対象であったとしても、反対株主が所持する株式の総数が総株式総数の1/6を超えている場合、また、分割承継会社が譲渡制限会社である場合で、譲渡制限株式を割り当てる場合は株主総会の実施が必要になります。
譲渡制限株式については複雑なので、必ず専門家に確認をするようにしましょう。
他にも、吸収分割の届出用件があり、当てはまる場合には公正取引委員会への届け出が必要になります。
基本的には売上によって届け出の有無が変わりますので、届出用件は公正取引委員会の分割の届出制度より確認するようにしてください。
簡易分割という選択肢
株主総会の実施をどうしても避けたいという場合には簡易分割という選択肢を検討するのもいいかもしれません。
簡易分割とは、株主総会の実施を省略できる会社分割の方法です。
譲渡資産合計が分割会社の総資産の20%以下で、分割承継会社から交付される株式が分割承継会社の純資産が20%以下の場合に簡易分割を利用できます。
吸収分割に必要な期間は?
吸収分割にはおおよそ1.5ヶ月〜2ヶ月の期間がかかると言われています。
また、注意点は、吸収分割では会社法によって定められた事項をクリアしていかなければならないことです。債権者保護手続きから公正取引委員会への届け出など細かい手続きが幾つもありますので、必ず一つずつ確認しながら行うようにしてください。
また、分割する事業の種類によっては「許認可の届け出」の提出が必要になることもあります。
吸収分割で必要な費用
吸収分割には以下の通りです。
登録免許税
承継会社、分割会社共に30,000円の登録免許税がかかります。承継会社の資本が変動する場合には、総資本額×0.7%がかかります。
専門家への依頼費
依頼する書類により金額は変動しますが、少なくとも10,000円以上の費用がかかります。
官報公告費
官報の公告費用は吸収分割の公告のみの場合は1行22字×24行で3,589円、合わせて決算公告の掲示(2枠)で37,165円の費用がかかります。
上記のような費用がかかります。
吸収分割で必要な労働契約の承継手続きについて
吸収分割では包括承継となるため、従業員との個別での協議は必要ありません。
しかし、労働者保護の観点から、労働者の理解と協力が求められています。このため、労働組合との協議が必要になります。
この際協議するのは、会社分割をする背景と理由等になります。
吸収分割契約とは
会社分割をする際は、会社のどの事業を分割するのかをしっかりと決める必要があります。
吸収分割契約書で決定するのは、承継させる事業、交付される対価、承継会社の資本金が増加する場合にはその額、効力の発生する日になります。
株主総会が不要な場合もある
株主総会が不要な場合は、既に説明したように簡易会社分割ができる場合です。
また、簡易会社分割以外にも、略式会社分割が適応される際には株主総会を省略できます。
略式会社分割とは、分割会社が承継会社の議決権を90%以上実質的に保有している場合には、株主総会を省略できるという制度です。
株主総会が必要か否かについては必ず確認するようにしましょう。
吸収分割の会計処理や税金は?
吸収分割の仕分・会計処理は非常に複雑であり、個々の事例によって変わってきます。
ここでは一般的な会計処理と吸収分割の税務処理について詳しく解説していきますので、参考にしてください。
会計処理の原則
会計処理については、個々の事例によって変わってきます。
基本的には、分割会社は借方に分割する事業の負債、承継会社からの株式、貸方には分割する事業の資産を記載し、その差を譲渡損益として記載します。
また、承継会社は譲り受けた資産と負債、そして支払った現預金、株式との差額を営業権(のれん)で計上します。この際の会計方法はパーチェス法を利用します。
パーチェス法とは企業の合併方法などに係る会計処理基準の一つです。合併先の資産・負債について時価評価し、その差を営業権(のれん)として計上します。
承継会社での仕訳処理には必要になりますので、頭に入れておく必要があります。
参考記事:
・のれんとは?M&A成功のために知っておきたい「のれん」の評価の高めかた、減損の防ぎかた
分割会社と承継会社との関係で会計処理は変わる
分割会社と承継会社との関係性によって会計処理は異なります。
(1)承継先が分割会社の子会社になるケース
承継先が吸収分割の対価として株式を交付した場合、承継先が分割会社の子会社になるケースがあります。
この際の会計処理は譲渡損益を取りません。負債と資産の差額(簿価評価)を子会社株式として計上することになります。
(2)承継先が分割会社の持分法適用会社になるケース
承継先が分割会社の持分法適用会社となる場合は、受け取る株式は関連会社株式となり、資産と負債の差額(時価計算)が関連会社株式となります。
このため、譲渡損益は発生しません。
(3)受け取る株式がその他の有価証券に該当する場合
上記の2パターンに当てはまらない場合には、資産と負債の差額(時価計算)をその他有価証券として引き継ぎます。差額は譲渡損益として計上することになります。
万が一、時価評価を誤り、譲渡損益を小さく算出してしまった場合には、その後不当に税金額を小さくしたとして追加で税金を徴求されるリスクがあります。
このように会社分割では非常に複雑な会計処理が必要になるため、詳細については必ず税理士に確認を取るようにしてください。
吸収分割の税務処理について
吸収分割の税務処理については以下3点がポイントになります。
(1)繰越欠損金について
「合併類似的各分割型分離」に吸収分割が該当しない場合には、繰越欠損金を引き継ぐことができません。
(2)法人住民税と事業税について
承継会社の資本金と資本積立金の合算が増加すると、税負担が増加する可能性があります。
資本金の増加が自社にとってどのような影響をもたらすかは必ず確認しておきましょう。
(3)不動産取得税について
会社分割により承継会社が不動産を取得すると、固定資産税評価額の4%分不動産の取得税がかかります。しかし、不動産取得税が非課税になる場合もありますので、合わせて確認をしておくようにしましょう。
出典:不動産取得税 Q&A「Q21 会社分割により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。」|岡山県
まとめ
本記事では会社分割の種類とメリットや注意点をわかりやすく解説しました。
一口にM&Aといっても様々な方法があります。最も大切なのは自社に合うM&Aの手法をとることです。会社分割でメリットが多いということであれば会社分割を検討してみてください。